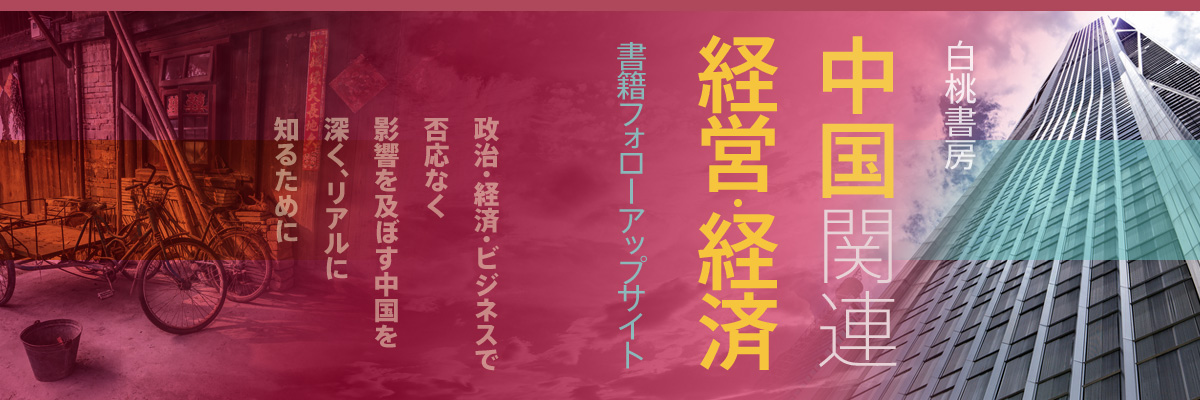今日では誰しも、中国経済が1970年代末以来の「改革開放」を経て、長期にわたり急成長をなしとげてきたこと、すでに購買力平価では米国を抜いて世界一の経済大国となっていること等の事実を知っていることだろう。他方で、すでに生産年齢人口の減少期に入っていることもあり、以前のような高い成長率を実現することが難しくなっているのではと考えている人も多いはずだ。さらに近年の米中対立の激化、習近平体制の今後などといった不確定要素も相俟って、現在、世界中の人々が中国の一挙手一投足に目を凝らしている。
今日では誰しも、中国経済が1970年代末以来の「改革開放」を経て、長期にわたり急成長をなしとげてきたこと、すでに購買力平価では米国を抜いて世界一の経済大国となっていること等の事実を知っていることだろう。他方で、すでに生産年齢人口の減少期に入っていることもあり、以前のような高い成長率を実現することが難しくなっているのではと考えている人も多いはずだ。さらに近年の米中対立の激化、習近平体制の今後などといった不確定要素も相俟って、現在、世界中の人々が中国の一挙手一投足に目を凝らしている。
だが、われわれはどれほど中国経済のことを知っているのだろうか。ここには大きな認識上のギャップがあるように思われる。西洋諸国とは歴史的にも、政治的にも大きく異なり、独自の発展を遂げつつある中国をどのように理解したらいいのかに、われわれは戸惑っているのではないか。このギャップを埋めるのに、まずもって必要なことは、この間の中国経済の激動の中で起こっていたことの本質を理解することである。本書『現実世界と対話する経済学』は、われわれにも理解可能な仕方で中国経済のダイナミクスを説明してくれるものであり、まさにこのギャップを埋めるための第一歩を提供してくれるものである。
著者の周其仁氏の経歴に関する詳細は、本書監訳者の梶谷懐氏による解説に譲ることとしたいが、特筆すべきことは、周氏がこの間の中国経済の激動のただ中を生き抜き、たびたび政策提言も行ってきた「当事者」の側面と、この体制転換のプロセスを整合的な理論的立場から見通す冷徹な「分析者」の側面を併せ持っているということである。実際、本書は中国経済がこの間経験してきた激動の貴重な記録として読むことができる。だが同時に、本書を一読した読者は、その分析の視点が高度な一貫性を保ち、きわめて洗練されていることに感銘を受けるだろう。
より具体的に内容について述べていこう。本書全体は13の章から構成されている。これを大きく分けるならば、5つの部分に分けられる。(1)最初の2つの章で、本書全体を貫いている新制度派経済学の方法論的枠組みが提示される。(2)第3章から第5章までは、中国建国後の農業政策と農業改革の歴史的・制度的分析、(3)第6章から第11章までは、中国における企業システムの理論的・実証的分析、(4)第12章は、他の章とはやや性格を異にする金融政策に関する分析、(5)そして最終章で、全体的な分析を回顧しつつ再び新制度派経済学の方法論に戻って、「体制コスト」という独自の概念で経済変化のダイナミズムを見通すことが提案されている。
本書で用いられる分析枠組みに馴染みのない読者のために、周氏が本書で主として依拠している「新制度派経済学」に関して、若干の解説を加えておこう。
20世紀の経済学の主流派は、市場という資源配分メカニズムの作用の仕方を数学的・抽象的なモデルによって理解しようとする「新古典派経済学」であった。しかし、第1章の副題にも現われ、本書全体の議論に大きな影響を与えているロナルド・コースは、すでに1937年の「企業の本質」という論文で、より現実的な経済学を展開する上で、抽象的な市場モデルの分析では不十分であることを説得的な仕方で述べていた。市場の働きにおいては企業が重要な役割を担っている。しかし、企業の存在は市場取引にコストがかからないような理論的枠組み——これが新古典派の市場理論の仮定である——では説明することができないのである。そこでコースは、市場取引にも一種の摩擦のような「取引コスト」が存在すると考えるべきことを主張する。同時に、企業における資源配分にも「組織コスト」が存在しており、市場の取引コストと企業の組織コストのの両者を勘案することで、現実経済の複雑な様相が理解できるとしたのである。このアプローチが経済学界で広く受け入られるまでにはかなりの時間がかかったが、その後、経済に対するこのアプローチは徐々に大きく発展して、市場に関する経済学者の見方を一新していくことになる。
この立場からは、市場はさまざまな制度にとり巻かれて機能しており、その制度のあり方によって、市場はうまく機能したり、機能不全に陥ったりするというパースペクティブが切り開かれる。こうした制度の中でも特に重要なのが、本書の原著のタイトルにもある「財産権」のあり方なのである。
新制度派の理論的枠組みの部分から見ていこう。第1章では、上述したコースの分析視角の意義と重要性がこれ以上ないほどのクリアさで説明されているが、著者は単にコースの議論を金科玉条のものとして受け取るのではなく、独自に発展させてもいる。たとえば、第2章で論じられる「人的資本」に関する見方は著者独自のものだが、本書全体を通して、何度も登場し重要な役割を果たしている。「人的資本」という概念自体は、主流派経済学でも経済成長の源泉をなすものとして重視されているものである。しかし、著者はこの概念を新制度派の枠組みと結びつける独自の議論を展開しているのだ。
同じ「資本」という言葉を含んではいるものの、人的資本はそれを保持し、活用する「意志」を持った個人と不可分であるという点で、物的資本と決定的に異なるものである。このような人的資本と個人との不可分性は、人々の労働意欲(=人的資本の活用意欲)を刺激することがきわめて重要であることを示している。この論理は、人的資本に対する財産権の如何にかかわることなく、どんな社会においても成立しており、中国経済における人々の経済活用に対する意欲に適用されている。
本書全体の中でも特に印象的だったのは、第3章から第5章にかけて展開される中国の農村・農業改革の経緯の分析である。読者の多くは、中国において人民公社が設立されて以来、中国農業が大きな危機に直面したこと、そして集体集団農業 (「集体農業」)が挫折し、ついには生産請負と引き換えに,土地を家族経営による生産——農業生産責任制(包産到戸)——に道を譲ったことを知っているだろう。本書におけるこの間の歴史の記述はきわめて詳細で読みごたえがある。上述した「人的資本」の論理をも援用しつつ、実は農民たちが「集体農業」において「部分的な退出権」を行使して、このレジームに対抗していたことが述べられている。また、われわれはこの間の農業改革の経緯を農民主導のボトムアップな改革のプロセスとして一面的に捉えがちだが、そこには「中央政府―地方政府―農村コミュニティ―農民」という多様な主体間の複雑なインタラクションから、新たなレジームが「取引」として生じていったことが詳細に述べられている。
こうした大変革は結果として財産権の構造変革を生み出した。しかし、この展開がさらに多くの問題を市場の深層において生み出していること、いまだに多くの矛盾が土地譲渡制度に残されていることなどが、第4章、第5章において分析されている。
1980年代を通して、中国が農業改革を通じて息を吹き返した結果、1990年代には工業生産においても大きな進展が見られたが、ここでも財産権の再配置が重要な課題となってきた。このことが、第6章から第11章で分析されている。
ここでも分析のベンチマークとなるのはコースの企業論だが、第6章において、周氏は企業を、人的資本に関する契約と非人的資本に関する契約が組み合わさった市場契約として見る独自の観点を確立する。先に見たように、人的資本は個人と不可分なために、企業にインセンティブ・メカニズムがうまく組み込まれていることが重要なポイントとなる。古典的企業から現代企業への歴史的展開を辿った上で、現代企業では、人的資本の相対的な地位の急激な上昇と、純粋な金融資本の相対的な重要性の低下が見られるという洞察も興味深い。
西洋的な基準からすれば、企業は株主によって所有され、経営者がインセンティブを付与されて株主から経営を請け負い、従業員も固有のインセンティブ・メカニズムのもとで働いているという構図を描くのが通常である。しかし、中国の場合には、産業発展の過程において公有制企業が歴史的に重要な役割を果たしてきた。また、このプロセスにおいて、単純な公有制企業とも異なる形態の財産権の配置を生み出してきたことも、重要なポイントである。
第7章では、どの個人も資産に対する所有権を手にしていない「コミュニティ所有制」という形態をとりつつも、カリスマ的な経営者・徐文栄氏が経営権を一手に収めて成功している横店グループのガバナンスを詳細に考察している。ここでは、経営者がわずかな残余請求権しか得られないにもかかわらず、どうして多大な努力を傾注して経営を行うのかという問いを立て、最終的には、コントロール権(経営権)そのものが報酬となり、インセンティブ・メカニズムとして機能しているという結論を導くとともに、そのようなシステムがどの程度まで存続可能なのかを考察している。移行経済において現われた、西洋的基準の観点からは非標準的な形態を持つ企業の動態分析として、きわめて興味深いものである。
ただし、市場化改革における公有制企業のあり方に対する周氏の最終的な評価は、厳しいものである。公有制企業では、財産は法律上は公有である。しかし、それと組み合わされる人的資本が個人によって保有されている以上、個人は公有制企業が生み出すレントを占有しようとする。その結果、事実上の私的権利が企業内部に発生してしまい、そのことが企業が生み出すレントの分配に大きな影響を与えてしまうのだ。そこで、最終的には個人の財産権を明確化する必要があることが論じられる。総じて、市場化改革においては、政府は行政的管理から手を引き、財産権を明確化して、企業に独立した経済的地位と経済的利益を認めるべきだというのが周氏の主張である。ここでの議論は、きわめて明確な理論的視点から展開されているが、第11章「病気になったら,誰が面倒を見てくれるのか?」では一転して、経験的事実の徹底重視によって議論を展開している点が印象的である。この経験的事実の重視もまた、コースの方法論の中核をなすものであって、それは決して方法論的に矛盾しているわけではない。徹底したデータ重視の視点から、中国の医療経済が抱える問題が市場化によって生じたものではなく、市場化が不徹底なことから生じていることがきわめて説得的に論じられている。
本書全体でやや外れたところにある第12章を挟んで、最終章において周氏は、本書で展開された多様な議論を「体制コスト」という独自の概念を提案することで展望している。ここで「体制」とは、システマティックに配置された一連の制度のことである。そして「体制コスト」とは、簡単に言えば、市場取引が孕んでいる「取引コスト」を体制全体に一般化したものであり、その体制がそこで展開される経済活動全般に課しているコストのことである。人々の行動選択に強い制約をかけることは、それだけ体制コストが大きいことを意味している。
この観点から、改革開放以降の中国経済の急速な発展を駆動してきた根本的要因が、さまざまな財産権改革を通して、それまで非常に高かった体制コストを低減させてきたことにあると総括される。だが、経済学で現われる通常のコスト同様、このコストも最初に下ってから再び上昇する傾向を持つようである。実際、周氏の診断によれば、今日の中国は、いったん削減された体制コストが再び急激に上昇している局面として理解することが可能だという。それはたとえば、さまざまな法的負担の増加、行政の許認可の増加、レント・シーキング行為の増加などに現れている。こうした観点から、現在の中国には体制コストの急激な上昇を抑制するとともに、それを低下させることが求められていると結論づけられる。中国経済のダイナミクスの根幹を見つめ、分析し続けてきた著者の大局的な経済観がここに語られていると言えるだろう。
本書において著者は、中国経済が辿ってきた特殊なダイナミクスを、ロナルド・コースらによって彫琢されてきた新制度派経済学の「普遍的」概念を駆使しながら、明晰な仕方で理解させてくれる。その点だけに焦点を当てると、著者が市場化を徹底すべきことを提案するとき、中国経済を西洋的概念によって理解可能な経済に変革することを提案しているように見えるかもしれない。しかし、おそらくそのような単純な見方は正しくない。
周氏の議論は、常に中国経済の特殊な状況に適用されている。そしてその議論においては、中国が西洋資本主義国とは異なる出発点から市場化を行っていることが強く意識されている。その意味で、市場経済や財産権に関する普遍的なロジックを用いながらも、中国における改革の経路を前提とした、独自の市場経済が目指されていると考えるべきである。その行き着く先は、われわれが知っている西洋的な資本主義とは異なるものである可能性が高い。
翻って見てみると、今日、われわれの資本主義経済はさまざまな難問を引き起こして、その問題解決を迫られている。資本主義国に生きるわれわれこそ、周氏が本書で提示している洞察力や大局観に学びつつ、改革への道筋を真剣に考えなければならないだろう。冒頭で、われわれの中国経済に対する認識のギャップを埋める第一歩として、本書の意義があることを述べた。だが、本書を繙くべきもう一つの理由は、われわれ自身がわれわれの経済に対する分析を、著者のような情熱と客観性を持って進めていかなければならないと思わせてくれる点にあるのである。
 |
瀧澤弘和/たきざわ・ひろかず 中央大学経済学部教授。東京大学大学院経済学研究科種博士課程単位取得修了。研究分野はゲーム理論、実験経済学、制度論、経済政策論、社会科学の哲学。著書に『現代経済学』(中公新書)、『経済政策論』(慶應義塾大学出版会、共編著)など。訳書に青木昌彦『比較制度分析に向けて』(共訳)、ジョン・マクミラン『市場を創る』(共訳)、ジョセフ・ヒース『ルールに従う』(いずれもNTT出版)、フランチェスコ・グァラ『制度とは何か』(監訳)、デイヴィド・ルイス『コンヴェンション』(いずれも慶應義塾大学出版会)など。 |
| 著・訳・監訳 | 周 其仁 著/劉 春發 訳 /梶谷 懐 監訳 |
|---|---|
| 出版年月日 | 2023/11/6 |
| ISBN | 9784561961420 |
| 判型・ページ数 | A5・400ページ |
| 定価 | 本体5636円+税 |