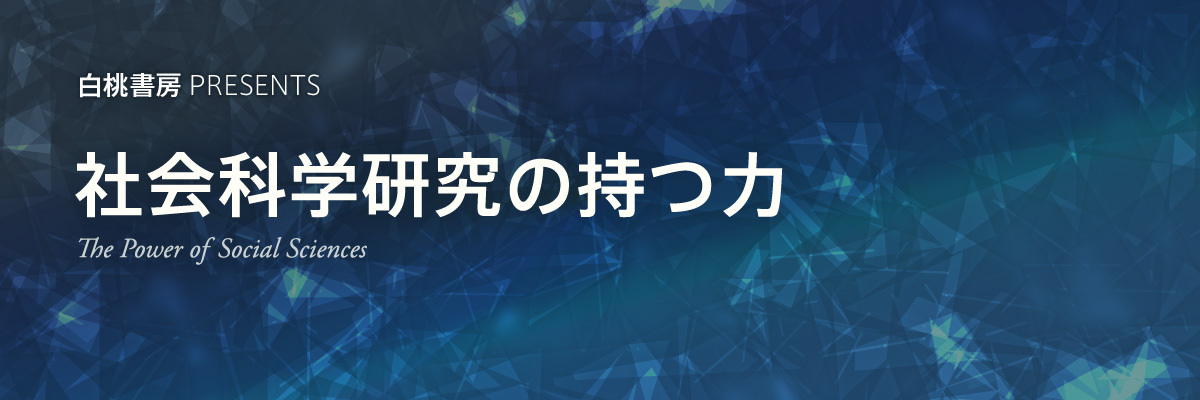【はじめに】
このコラムを読んでくださる方は、初めてのゼミで「論文」という得体の知れないものに触れた学部生の方でしょうか、あるいは卒業論文を前にして途方に暮れている4回生の方かもしれません。はたまた、大学院に入って研究に向き合おうとしてはいるのだけれど、指導教員に「この研究の何が面白いの?」と言われてしまって迷走している院生さんもいらっしゃるかもしれません。
以下では、近年の良著のなかから、論文を書く/研究をするという営みについて考える上でおすすめの4冊をピックアップしています。いずれの書籍も、私が院生生活のなかで実際に手に取って学びになったもの、また同僚や後輩のあいだで有用として高い評価を得ているものを選びました。それでは、やさしい順に紹介していきましょう。
(1)佐藤郁哉著『リサーチ・クエスチョンとは何か?』(ちくま新書、2024) 佐藤郁哉著『リサーチ・クエスチョンとは何か?』ちくま新書
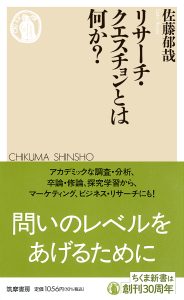
そして本書は、それらのエッセンスが詰まった1冊 にあたる。問いの立て方や研究の進め方に関する本は数あれど、本書が他の本と一線を画すのは、「問いに基づいて調査を進めていき、最終的に論文の形に仕上げる」という一連の過程のバックヤードの部分、いわば研究のブラックボックスの中身が丁寧に描かれている点だ。本書の表現にならえば、「問いの立て方」だけではなく「問いの育て方」こそが重要なのである。
このように本書では「舞台裏でおこなわれる作業に含まれる不確定で不確実な要素も考慮に入れながら何とかして問いを育てていく作業の要点やコツ」が解説されていくのだが、一口に「問い」といっても、様々な種類がある。記述的な問い(What)なのか、説明的な問い(Why)なのか。それとも改善策(How to)を求めているのか……。あるいは考えるべきは、結果としての問いなのか、それとも経緯における問いなのか……。本書は、こうした曖昧さがつきまとう「問い」をひとつひとつ整理した上で、それらをどのように組み合わせ、研究に落とし込んでいくべきかを導いてくれる。
研究を進めるにあたって、自らの関心がどこにあり、どのゴールを目指そうとしているのかを自覚していなければ、論文執筆というプロセスも暗中模索の手探り状態になってしまうだろう。本書はそのプロセスをダイナミックなものとして捉え直し、その解像度を上げてくれる良書である。加えて、本書は図解がどれも秀逸だし、文章もとても分かりやすい。研究の入り口に立つ社会科学系の学部生の方にまずおすすめしたい1冊だ。
(2)小熊英二著『基礎からわかる 論文の書き方』(講談社現代新書、2022) 小熊英二著『基礎からわかる論文の書き方』講談社現代新書
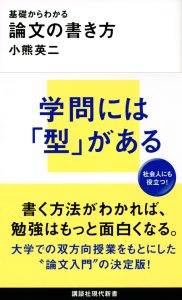
本書の特徴は、社会科学のみならず人文学や理系までひろく視野に含めながら、論文の共通の型と役割を明らかにする点にある。IMRAD(この言葉を聞いたことがない読者は今すぐ書店へGO!だ)に代表される論文の「型」は、主題と対象と方法を明確かつ論理的に他者に伝えるという目的を果たすためにこそ設けられているのである。料理のレシピになぞらえながら進む説明も腑に落ちるものばかりだし、各章のポイントが章の冒頭 に1頁でまとめて整理されているのも地味にありがたい。
こうした論文の「基礎」が理解されれば、「どう書くのか」という問題も解決可能だ。本書でも、より生産的なゼミ資料の作り方や口頭発表のコツ、ゼミでより良いコメントをする時に気をつけること、要旨や目次に求められる要素などなど……学生にとってはありがたい知見が盛りだくさんである。実際のところ、私は学部生ゼミのアシスタントを務めていた際に本書を繰り返しお勧めしてきたのだが、本書の内容は学部生にとっても役立っていた ようだ。場当たり的な感想ではなく、研究を前に進めるための生産的な発言が増えたのは、間違いなくこの本のおかげである。
つまるところ、論文執筆において求められるのは、自らの主張を論理的な文章として根拠づけて、わかりやすく読み手を説得する能力なのだ。これは論文執筆に限らず、交渉やプレゼンといったビジネスの場面にも転用可能な一生もののスキルだろう。読者のレベルや学問分野を問わず、バランス良く論文の書き方を学べる大学生必携の書である。
(3)阿部幸大著『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』(光文社、2024) 阿部幸大著『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』光文社
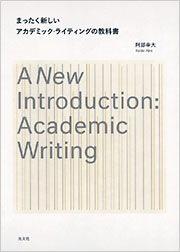
まずは、刊行と同時に話題を集めた『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』。SNSで見かけた方も多いだろう。本書はとても読みやすく、また極めてわかりやすいので、学部生でもすらすら読めるはずだ。
とはいえ、この本が真価を発揮するのは、実際に投稿論文を執筆し始めた院生においてだろう。というのも、本書は単に「文章術」の紹介に終始するのではなく、実際にいかに論文を書き、学術ジャーナルに投稿していくのか、という極めて実践的な「執筆論」を展開しているのだ。本書は、原理編と銘打たれた「学術的な価値とは何か」「論文を書くとはどのような営みなのか」という議論から始まる。著者の切れ味抜群の議論は一読の価値ありだ。これほどまでに明瞭に論文の意義を論じた類書を私は知らない。
ちなみに、著者はこの原理編で「問いの有無は論文の成否における条件とは本質的に関係がない」と述べている。ここまでこのコラムを読んでくださった方は、「え?」と思われるかもしれない。「(1)では問いが大事だと言っていたじゃないですか」と。しかし、実は両書はそれほど矛盾していることを述べているわけではない。ぜひ重ねて読んで、論文執筆の本質を味わってほしい。
さて、巷のアカデミック・ライティング系の書籍では、主述の一致やパラグラフ・ライティングの重要性など、「それは知っているんだけど、実際にやるのが難しいんだよ……」という情報が多いように感じられる。それに対して、本書は、先行研究をいかに読み、どの部分をいくつ引用すればいいのか?パラグラフの連なりをいかに作ればいいのか?といった、大半の院生が直面しているであろう悩みに応えてくれる。
本書では、アンパンマンについての論文を書くプロジェクトを実例として講義が進むのだが、筆者の実績と経験に裏付けられた説明は非常に説得力があるし、アドバイスはどれも泥臭く、そして地に足がついている。その詳細は実際に本書を繙いてもらいたいが、一読の価値がある良著であることは請け合いだ。
(4)M.アルヴェッソン/J.サンドバーグ著、佐藤郁哉訳『面白くて刺激的な論文のためのリサーチ・クエスチョンの作り方と育て方 論文刊行ゲームを超えて 第2版』(白桃書房、2024) M.アルヴェッソン/J.サンドバーグ著、佐藤郁哉訳『面白くて刺激的な論文のためのリサーチ・クエスチョンの作り方と育て方 論文刊行ゲームを超えて 第2版』白桃書房

本書は、「なぜ『一流誌』の論文は退屈でつまらないのか?」と問いかける。社会科学においては、ギャップ・スポッティング的な――先行研究の未解決点の隙間を見つけ出してそれを埋めるための――論文が増えていると著者らは分析する。それは先行研究の前提を容認・補完するもので、ある意味では堅実かもしれない。しかし彼らは言う、それでは「面白くない」のだと(私も身に覚えがある)。それは「既存の理論や先行研究の根底に対して挑戦するのではなくむしろそれらを再生産する傾向があるので、面白い理論の開発につながる可能性は低い」のだ 。
本書が主題とするのは、IF値(Impact Factor:被引用数などによって計算される学術雑誌の格)よりも本質的なインパクトである。重要なのはギャップ・スポッティングではなく、学問を前に進める新たな理論を生み出す創造的破壊なのだ。既存の理論の根底にある前提に光を当て、それを「問題化」し、乗り越える研究が求められている。
では、その「問題化」をどのように行えばよいのだろうか? 本書は、この「問題化」という方法論をめぐって展開する。既存のギャップ・スポッティング的な問いを批判的に解析し(敵を知るという意味で、この部分も非常に読み応えがある)、「問題化」の実践例を取り上げ、しまいには「なぜ面白い理論の構築にとって逆効果でしかないギャップ・スポッティング的アプローチが支配的になっているのか?」と、この学術界のトレンドそれ自体に「問題化」を行っている。若手研究者の一人として、非常に刺激をもらい、研究者としての在り方を考えさせられた一冊だった。
【結びにかえて】
ここまで論文執筆に役立つ4冊を紹介してきました。いずれの書籍も、私自身も非常にお世話になった本です。読者の皆さんにとって少しでも参考になれば幸いです。そして最後に、一院生の立場から、こうした問いや研究についての本が持つ、より大きな意味について付言しておきます。
それは、研究の構造や問いの解像度を自覚的・批判的に扱う言葉を手にすることで、ゼミ全体の議論の質が上がっていくという効果です。ゼミのなかで目指すべき論文の型や最低限表現されるべき情報が共有されていれば、次第にレジュメや資料の論理的なクオリティも上がっていく。そうなれば瑣末な「確認」や「感想」を省くことが出来るし、その分、新しいことを「生み出す」ことに思考と時間のリソースを割くことができる。この積み重ねは決して馬鹿になりません。
この4冊はそれぞれ重点の置かれた方やレベル設定は異なれども、いかにより良い研究を生み出していくのか、いかに学問を前に進めていくのかというエッセンスを研究の先達が言語化したものであるという点は共通しています。これらの知見はどれも一般化可能なものですから、読者自身の研究だけでなく、他者の研究をどう良くしていくのか、という目線においても非常に効果を発揮するでしょう。いずれも議論全体の質を高めるために、共有知として本棚に加えてほしい良著です。
(2025年1月14日公開)
| 水野遼太郎/みずの・りょうたろう 京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程在籍。専門は社会学。人口減少が社会にもたらす影響、特に地域コミュニティの時間/空間的な変容と人々の実践との相互作用について、過疎地域でのフィールドワークやインタビュー調査をもとに研究を行っている。 https://researchmap.jp/ryotaromizuno |