〔『激動の時代のコンテンツビジネス・サバイバルガイド』書籍紹介ページ〕
まったく別の著者による「続・FREE」
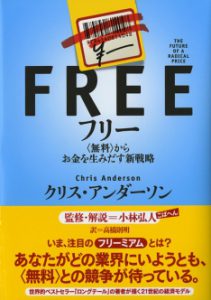 本書を読みはじめると、これに似た本を前に読んだなあと思い出した。そうだ、クリス・アンダーソンの『FREE』(『フリー〈無料〉からお金を生みだす新戦略』)だ! すぐにそう気づいた(実際に本書にはクリス・アンダーソンの名前も「ロングテール」の提唱者として登場する)。調べると、 日本での出版は2009年だったのでちょうど10年前だ。本書はまったく違う著者による『FREE』の続きだと言えるかもしれない。同じようにコンテンツやメディアについて書かれた本であり、古今東西の豊富な事例が具体的に織り込まれている。そして同じように、この分野のビジネスモデルを探求する内容だ。10年前に『FREE』にハマった私としては、だから読みやすくあの時に似た知的興奮を感じながら読み進められた。私同様『FREE』を面白く読んだ人なら、まさにその続きとして本書を受けとめるのではないだろうか。
本書を読みはじめると、これに似た本を前に読んだなあと思い出した。そうだ、クリス・アンダーソンの『FREE』(『フリー〈無料〉からお金を生みだす新戦略』)だ! すぐにそう気づいた(実際に本書にはクリス・アンダーソンの名前も「ロングテール」の提唱者として登場する)。調べると、 日本での出版は2009年だったのでちょうど10年前だ。本書はまったく違う著者による『FREE』の続きだと言えるかもしれない。同じようにコンテンツやメディアについて書かれた本であり、古今東西の豊富な事例が具体的に織り込まれている。そして同じように、この分野のビジネスモデルを探求する内容だ。10年前に『FREE』にハマった私としては、だから読みやすくあの時に似た知的興奮を感じながら読み進められた。私同様『FREE』を面白く読んだ人なら、まさにその続きとして本書を受けとめるのではないだろうか。
『FREE』とは違う部分ももちろんある。クリス・アンダーソンが元WIREDの編集長でありメディアビジネスの当事者であるのに対し、本書の二人の著者は大学教授つまり研究者だ。そのため本書では突然、統計学を駆使した緻密な分析がグラフとともに書き綴られたりする。あくまで現場の人間として語り続ける『FREE』と、そこは大きく違う点だ。その分、こちらのほうが実証的で説得力もある。グラフが出てくる論文調の文章は苦手だと腰が引ける人もいるかもしれないが、そこは安心してほしい。私も小難しい文章は大の苦手だが本書はスルスル読めたからだ。決して学術論文ではないので、その点は気にせず読めると思う。
各章がコンテンツビジネスのホットなテーマ
大学教授の肩書を持つ二人の著者が書いたとはいえ、本書の章立てにはちょっとしたウィットが込められている。各章のタイトルが「名作」の題名になっているのだ。第1章は「ハウス・オブ・カード」。言わずと知れたネットフリックス の大ヒットドラマだ。この章はタイトル通りまさにこのドラマがいかに掟破りなプロセスを経て誕生したかを詳細にレポートしている。第2章は「バック・イン・タイム」。これもオールド世代なら知らないはずのないロックバンド、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースの楽曲で「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のエンディングに使われている。この章では、現在のような 音楽産業が人類史に誕生した19世紀終わりから20世紀初頭の歴史を紐解く。章のタイトルは音楽業界の歴史を振り返る中身をうまく表現しているのだ。
コンテンツビジネスの本の各章に、コンテンツにまつわる粋なタイトルがついている。(第5章だけ邦訳では原題と違うタイトルになっているのは謎だが )大学教授のわりになかなかセンスがいいじゃないかとニヤニヤしてしまう。だがそれより重要なのは、本書の構成だ。各章がはっきりした主題を持っている。
例えば第6章は「レイズド・オン・ロバリー」。これはジョニ・ミッチェルの楽曲からとったらしく私は原曲を知らなかったのだが、この章では海賊版についてみっちり語っている。「海賊版は事業者にとって、あるいはユーザーにとって良いものか悪いものか」を徹底的に分析しているのだ。だから、とりあえず海賊版のことから読みたい、という人は第6章から読んでもいいだろう。また、あとで、あの本の海賊版について書かれた箇所はどこだっけ?と迷うこともない。目次を見れば、第6章だったとすぐにわかるのだから。
第9章「マネーボール」はブラッド・ピット主演の、メジャーリーグにデータ主義を持ち込んだゼネラルマネジャー を描いた映画からとったタイトル。この章では、プラットフォーマーたちがいかにデータを重視してユーザーを引きつけているかを書いている。データ活用について熟慮したければこの章だけあとで読み返せばいいだろう。
そんな風に、粋なタイトルがつけられた各章が明確な題材を扱っていることは、本書の読書価値を何重にも高めてくれそうだ。一種の“教科書”として数年間しゃぶりつくせるだろう。そういえば『FREE』も私は部分的に何度も読み返したものだ。その点もまた似ているのかもしれない。
コンテンツビジネスを考える脳みそを刺激する活性剤
「そうだったのか!」「そういえばそうだよな!」そんな独り言を、私は本書を読みながら何度か実際に口にしていた。コンテンツビジネスについて語ること、メディア論を誰かと戦わせることがなぜ面白いのか。私が思うに、格好のクイズだからだ。メディアの未来を考えたくなるのは、これほど知的刺激に満ちた頭の体操もなかなかないせいだと思う。そして本書の醍醐味は、その頭の体操のヒントを次々にくれる点だ。
私がいちばん大きな声で「そうだったのか!」と口に出していったのは、第2章だった。そこでは先述の通りヒューイ・ルイス&ザ・ニュースの楽曲「バック・イン・タイム」のタイトルの下、音楽業界ができあがって発展する歴史が事細かに描かれる。1877年にエジソンが蓄音機を発明したのが発端だが、それで一気にレコード産業が開花した、わけではなかったのだ。様々な起業家や発明家がエジソンの蓄音機に改良を重ね、事業モデルを構築しては失敗もし、裁判で争ったりもした。その判決が1901年に出て以降、ようやく円盤に音楽を記録し回転させて再生する「レコード」が普及した。エジソンの発明から20年以上経っているのだ。その時、市場を形成した2大勢力がコロンビアとビクターだった。
そうだったのか! レコード産業が花開くまでに最初の発明から20年以上かかっているのか! しかも音楽産業の趨勢は20世紀初頭には決定し、いまもその名があるレコード会社がすでに牛耳っていた。ビジネスモデルの模索がいかに大変で、そこで勝利した成果は大きいことがよくわかった。
そんなことを本書から知ると、私の頭の中では猛烈な勢いで今に置き換えて物事を考えていってしまう。インターネットが登場してから20年以上経っているが、これからますますいろんなことが起こるのだろう。 レコードが普及するのにそんなにかかっているし、数量的に大爆発するのはさらにその数十年後だ。だとすると、今起こっていることはまだ端緒にすぎない。ではこれからどうなっていくのだろう。そんな風に未来に想いを馳せてしまう。
もう一箇所、「そうだったのか!」と叫んだ箇所を紹介しよう。第4章「パーフェクト・ストーム」。ジョージ・クルーニー主演の巨大タイフーンを描く映画をタイトルにしたこの章では、物語の中で台風が重なって空前の規模になったように、デジタルの嵐もいくつか重なったからこそ社会を変化の大波で襲ったことを書き綴っている。その中で、90年代のAT&Tの社員だったハウイー・シンガーとラリー・ミラーが「a2bミュージック」というサービスを企画したエピソードが出てくる。デジタル音楽ファイルをインターネット経由で配信する、という考え方で、シンガーとミラーは、これはユーザーに便利この上ない音楽の楽しみ方を提供できると音楽業界に説明した。ところが、業界関係者の逆鱗に触れてしまったというのだ。「a2b」とは「アトム・トゥ・ビット」のことだが、音楽業界の経営幹部は『自分たちの音楽が「ビット」と称されると侮辱と感じる』 」と言い放った。
そうだったのか! このエピソードはのちにiTunesが音楽流通に革命をもたらしたことを思うと少しだけ早すぎた発想だったわけだが、私が驚いたのは業界関係者の反応だ。いまの日本のメディア業界でもほとんど同じような議論が繰り返されている。実際、日本の各メディアで新しい取り組みに挑む社員たちが、上司や古参社員たちから感情的に怒鳴られてしまう、という話はよく聞く。アメリカは変化に柔軟なイメージを持っていたが、いちばん最初には今の日本と同じような反応がやはりあったのか、という驚き。そして90年代のアメリカで起こったことが2010年代の日本で起こっているなんて、遅すぎではないか、という二重の意味で「そうだったのか!」と私は叫んでいた。
このように、この本にはメディアやコンテンツビジネスの古今の事例が満載で、そのひとつひとつが驚きと刺激を私たちの脳に与えてくれる。そこから新たな発想も湧くし、忸怩たる思いも感じたりする。脳みそが跳ねたり弾けたり、大いに活性化させられる。
デジタルトランスフォーメーションという「新たなる希望」
本書の第3部では、これからどうすればいいかが結論的に書かれている。第3部には「新たなる希望」というタイトルがつけられており、これも言わずと知れた77年公開の最初の「スター・ウォーズ」に後年つけられた副題だ。ルークとハン・ソロがレーア姫を救い出して戦士として認められたラストシーンのように、第3部を読めばコンテンツビジネスの戦士として戦いに行けるのだ。
そこで語られているのは、流行りの言葉で言うと「デジタルトランスフォーメーション」だな、と私は受けとめた。誤解のないように書いておくと、本書の中にはこの言葉は全く出てこない。二人の著者は、そんなつもりは毛頭ないだろうし、この本を書き進めている時はまだあまり世間で使われてなかった言葉かもしれない。
恥ずかしながら、私自身もこの言葉の意味はつい先日理解した(ような気になった)ばかりだ。ただこの「デジタルトランスフォーメーション」とは、単なる「アナログをデジタルにする」ということではなく、デジタルの力を駆使して引き起こすビジネスモデルの大転換、とでも言うべき概念だと認識した。そして第3部で語られているのはまさに、コンテンツ産業、メディア企業がこれから否応なく新しいビジネスモデルへの転換を図ることになり、そのためには組織をどう変えればいいか、マーケティングの様々な部分をどう再構築すればいいか、ということだ。ある意味実践的であり、だからこそ抽象的でもある。実際に自分の事業や会社に落とし込むには、書いてあることの自分なりの変換も必要になるだろう。
ただひとつはっきりしているのは、デジタルによってコンテンツ界は“顧客”と向き合わざるを得ない、ということだ。それはデータの形をとって我々に何らかの対処対応を迫ってくる。第3部で二人の著者が切々と語っているのは、つまりはデータを通して顧客に向き合うべきだとのメッセージだ。
コンテンツの作り手、メディアの担い手はよく、データからは何も生まれないと口にする。それは過去の興行データやテレビ番組の分刻み視聴率のことを言っているのだろう。だがそんな愚痴ははっきり誤りだと私は思う。ヒットメーカーほど何らかのデータをとても気にするものだ。あるいは、まったくデータを見ないで創造する人はいない。データを見ないと言ってる人は自覚していないだけで、実は誰しも自分なりに人びとの反応をデータから受け止め、それを元に次の創作に向かうのだ。創作が人びととの心の通い合いである限り、データは必要なのだ。この本を手にするコンテンツ業界、メディア事業の担い手の皆さんはぜひ、そんな気持ちで第3部を読んでもらいたい。データを通じて、人びとの心を読み取ろう、気持ちの襞を知ろう。それを駆使した、ビジネスモデル転換の時代がやってきている。
 |
境 治(コピーライター/メディアコンサルタント) 1962年福岡市生まれ。東京大学文学部を卒業後、1987年、広告代理店I&S(現I&SBBDO)に入社しコピーライターとなる。1993年に独立。2006年から株式会社ロボット、2011年からは株式会社ビデオプロモーションに在籍。2013年7月から、再びフリーランスになり、メディアコンサルタントとして活動。2014年より株式会社エム・データ顧問研究員。 著書に『拡張するテレビ ― 広告と動画とコンテンツビジネスの未来』『爆発的ヒットは“想い”から生まれる~SNSから始める新しい時代のマーケティング』。 |
| 書名 | 激動の時代のコンテンツビジネス・サバイバルガイド プラットフォーマーから海賊行為まで 押し寄せる荒波を乗りこなすために |
 |
|---|---|---|
| 著者・訳者・解説 | マイケル D. スミス・ラフル テラング 著 小林 啓倫 訳 山本 一郎 解説 |
|
| 出版年月日 | 2019/06/26 | |
| ISBN | 9784561227298 | |
| 判型・ページ数 | 四六判・280ページ | |
| 定価 | 本体2500円+税 | |
