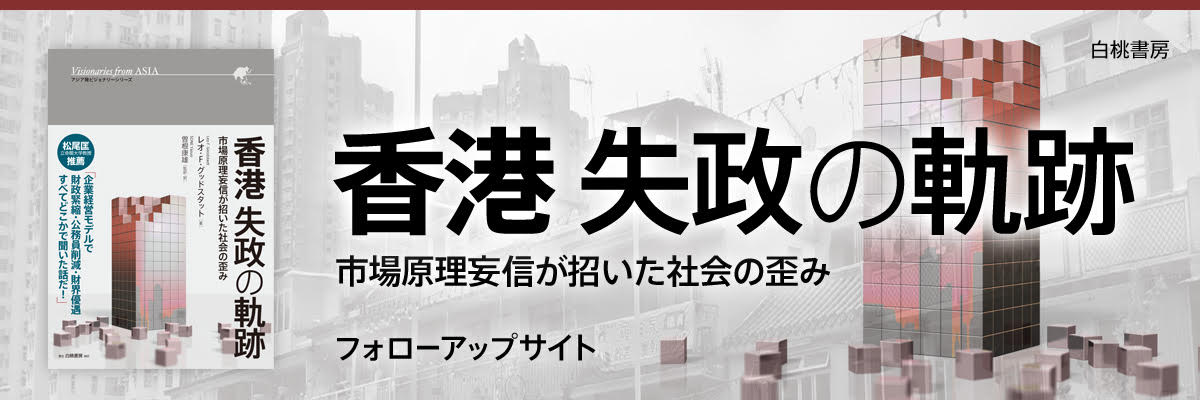1.著者について
1.著者について
『香港 失政の軌跡──市場原理妄信が招いた社会の歪み』は香港大学出版社 Hong Kong University Press から2018年に出版された Leo F. Goodstadt, A City Mismanaged: Hong Kong’s Struggle for Survival を全訳したものである。同書は、2019年3 月に香港で中国語(繁体字)版(『失治之城─掙扎求存的香港』)も出版されており、その際に情報をアップデートするため加筆された段落が若干ある。本書はこの版の出版社である天窗出版の許諾の下、原則として中国語版の加筆箇所も収録した。
著者のレオ・F・グッドスタット Leo F. Goodstadt 氏は、英国のオックスフォード大学とマンチェスター大学で経済学を修め、1962年に Commonwealth Scholar として香港に赴任、香港大学で教鞭をとり(62~64年)、後に同大学のアジア研究センター Centre of Asian Studies で研究に従事した。また、1966年からの10年間は、Far Eastern Economic Review 誌の副編集長を務め、文化大革命期の東アジア情勢を世界に向けて発信しジャーナリストとして名を馳せた。さらに、1967~73年にはTimes 紙、78~88年には Euromoney 誌の特派員をそれぞれ務めた。
1989年に香港政庁(英国植民地時代の香港統治機関)のシンクタンクである中央政策組 Central Policy Unit が設立されると、ジャーナリスト・研究者としての実績を買われ、当時のウィルソン総督から責任者に任命された。天安門事件から1997年の返還まで、香港政庁に政策提言を行う重要な役割を果たした。
1997年の中国への返還後、拠点をダブリンのトリニティ・カレッジに移したが、頻繁に香港を訪問して調査・研究を続け、多数の著書・論文を通じて中国に返還された後の香港の政治・経済・社会状況を分析し発信してきた。1960年代から英国植民地統治下の香港で研究活動を行い、最後には行政の意思決定に影響する立場にあったグッドスタット氏は、返還後の香港の行く末を案じつつも、本書で述べているように、多くの困難を乗り越えてきた香港が将来においても生き残る survive ことを信じてきた。
本書の序文でも記されている通り、同氏の香港でのキャリアは不動産部門の分析から始まった。香港の不動産・住宅問題は同氏のライフワークの一つとなり、本書でも多くの紙幅が割かれている。後述するように、香港の土地制度や不動産市場の構造を抜きにして、香港経済の仕組み、政府と財界の関係を理解することはできない。

グッドスタット氏ウェブサイトより
グッドスタット氏は本書の中国語版が出版された1 年後、そして日本語版の翻訳作業中であった2020年4 月にダブリンで逝去した(享年82)。本書は図らずもグッドスタット氏の遺作となった。半世紀以上にわたり香港を見つめてきた一人の英国人研究者は、その最晩年に起きた香港の政治的混乱をどのような思いで見ていたのだろうか。
2.利益共同体の政府・財界
グッドスタット氏は、返還後の歴代行政長官とその閣僚によるさまざまな施策を批判的に考察し、香港社会が抱える問題を香港市民の目線から抉り出している。本書が一貫して主張している返還後の香港政府の施政の問題点は、(1)均衡財政への固執、(2)「市場の力」market force(市場原理)の妄信、に集約することができる。香港基本法第107条が規定している均衡財政の原則を忠実に実行したがゆえに、緊縮財政を貫徹し、その結果、本来必要とされる予算や人員が削減され、行政サービスの低下を招いた。返還後に導入された「高官問責制(POAS)」や「生産性向上プログラム(EPP)」が招いた行政組織内の混乱も、それに拍車をかける形となった。「市場の力」に委ねれば最大限の効率を発揮できるという信念は、社会サービスの利用者に不利益をもたらす一方、不動産開発業者や民間教育業者などの既得権益を温存することになった。

狭小住宅を訪ねた政務司司長当時(2013年)の林鄭月蛾(香港政府新聞網提供)
これらの失政 mismanagement のしわ寄せを受けたのは、言うまでもなく香港の一般市民である。住宅の供給不足により「スラム」と形容される狭小住宅で生活せざるを得ない人々、十分なサービスを受けられない高齢者、高額の負担を強いられる医療サービス利用者、学力に見合う高等教育を受ける機会を奪われた若年層などである。さらに、失政は、SARS対策や建物・交通の安全をも脅かし、尊い命が失われるという事態まで招いたという。それらの中でも特に、高等教育の機会を奪われ、それゆえ十分な収入を得られる職業に就くことができず、また、将来の持ち家の希望も持つことのできない若年層は、香港政府の失政の最大の被害者であると言える。こうした将来への悲観や既存の体制に対する不満が、近年の若年層による激しい抗議行動の背景にある。多くの市民が若者の抗議行動に対して理解を示すのも、政府・財界といったエスタブリッシュメントに対する不満や反感が根底にあるからであろう。
米国のトランプ大統領の誕生や英国のEU離脱を契機に、この数十年間のグローバル化や新自由主義的政策の中で「取り残された人々」の存在に注目が集まった。中国はグローバル化 Globalization の波に乗って目覚ましい経済発展を遂げ、香港のマクロ経済および金融市場は中国本土の経済発展に貢献すると同時に、その恩恵に与っている。しかし、生み出された富の流れ着く先は、中国本土での事業拡大を進める財閥や金融機関に集中する。その一方で、経済発展の利益を享受できずに住宅や教育で不利益を被る「取り残された人々」が存在する。香港における政府・財界(エスタブリッシュメント)と市民との分断、21世紀に入ってからの抗議活動は、グローバル化という世界的な文脈でも捉えることができよう。香港は世界の中でも稀にみる国際都市であり、国際金融センター、アジアにおけるビジネス拠点として栄えてきただけに、「グローバル化の光と影」がことさら際立って体現されてしまった。
19世紀以来、香港政庁は経済発展の基礎となる港湾インフラの整備など、本来政府が担うべき最低限の事業の多くを、政庁のエージェントとして財閥に担わせていた。とりわけ香港特有の土地制度を通じて香港政府と財界の間に利益共同体の関係が築かれた。
香港の土地は一部を除いて原則として全て英国女王が所有し、香港政庁が管理してきた。そして土地の使用権(リース権)を民間に期限付きで売却し、その土地に対して、レイツ Rates と呼ばれる税金を賦課していた。従って、唯一の土地供給者である香港政庁は、土地使用権の売却益に加え、レイツといった土地関連収入を財源とすることができた。政庁が土地売却量を抑制すれば不動産市況が高騰し、不動産評価額が上昇するため、政庁の税収は増大した。戦後、中国本土からの移民の流入、貿易業・製造業の発展により、居住用、商業用、工業用の不動産需要が継続的に膨れ上がった。香港政庁は不動産価格の上昇を期待する傾向にあったため、高い土地費用が製造業など他業種の企業を圧迫し、自己防衛や利潤追求から不動産開発業への参入を誘発する循環構造が形成された。
1970年代末には、財政収入の約35%が土地関連収入で占められ、これが国際金融センターの必須条件である低税率を可能にした。中国本土からの移民流入による人口増加の中で、土地制度と住宅政策が今日の有力な華人財閥の勃興を促した。
中国への返還後、香港の土地は英国女王に代わり国家の所有(香港特別行政区政府が管理)となったが、土地供給の仕組みは継承された。こうした歴史的背景を踏まえて見ると、中国への返還と同時に初代行政長官の董建華が公営住宅の供給増加策を打ち出したことは、財界よりも市民の利益を優先する政策として画期的であり、当然ながら市民に歓迎された。しかし、1997年のアジア金融危機を境に財界の抵抗・圧力に屈することになった経緯は本書の第4 章で述べられている通りである。
なお、不動産開発を主要事業とする財閥が香港の実質上の「支配階級」であるという指摘はとくに目新しいものではない。近年こうした構造を問題視する著作が英語で出版されている。例えば、Alice Poon, Land and the Ruling Class in Hong Kong(2005, second edition 2011)および Yue Chim Richard Wong, Hong Kong Land for Hong Kong People: Fixing the Failures of Our Housing Policy(2015)、などである。中国への返還時に「香港人が香港を統治する」(「港人治港」)ことが原則とされ強調されたが、実際には「商人治港」になるのではないかと揶揄する見方もあった。その見通しはあながち間違いではなかった。
3.「自由放任主義」というハンディ
英国の植民地・香港を統治した香港政庁は「自由放任主義(レッセフェール)」laissez-faire の下、低税率と均衡財政を維持し、政府は企業活動には全く介入せず、企業は市場原理のみに基づいて経済活動を行うという原則を貫いた。
自由放任主義は、1970年代のマクレホース総督の時期(71~82年)に若干の変化をみる。本書でも説明されている公営住宅の供給やニュータウンの建設、交通インフラや工業区の整備、教育・技術支援などが本格化した。もっとも、当時のハドンケイブ財政司〔財政長官〕はこれを「積極的不介入主義 positive noninterventionism 」と呼び、政府の役割は純粋な公共財の提供と環境整備に徹することとした。宗主国の英国では1980年代にサッチャー首相のもとで「小さな政府」を標榜する新自由主義 neo-liberalism 的政策が始まり、やがてそれは先進諸国の潮流となったが、その原型は植民地・香港で実践されてきたものだったと言うこともできよう。
香港基本法は中国への返還後の香港の憲法に相当すると言われる。もっとも、通常の主権国家の憲法とは異なり、制度や政策について具体的な方針が定められている。その意味では香港統治のガイドラインと言った方がよいかも知れない。基本法では、植民地時代の法制度をはじめ、資本主義の制度、低税率政策、資本の内外の自由な移動などを維持することが細かく明記され、「レッセフェール」の原則を存続することが保証されている。
それは、中央政府や中国企業にとっても都合が良かった。「一国二制度」という枠組みで、英国統治下の香港の機能を存続させることは、中国本土の継続的な発展にとって必要なことであった。もっとも、香港基本法は、1980年代の香港の社会構造、中国本土の経済水準を前提として制定された法律である。1980年代までの「レッセフェール」「積極的不介入主義」は、21世紀に入ると香港の社会構造の大きな変化に対応できなくなってきていた。
本書では詳しく触れられていないが、「レッセフェール」の見直しをめぐり、返還後の香港ではしばしば論争が起きた。「自由放任主義」の下では企業の活力維持が優先され、最低賃金制の必要が指摘されても、経済界からの猛反発により立ち消えとなっていた。そうした中、曾蔭権行政長官は、2010年に最低賃金制の導入に踏み切った。曾の下で従来の方針が転換されたことは、「レッセフェール」の見直しとして議論を呼んだ。
さらに2015年には梁振英行政長官が、今後の香港経済の発展のためには「自由放任主義」を放棄し、企業活動への政府の介入を促進すべきだと発言し、物議を醸した。梁は香港の住宅不足は「自由放任主義」が生み出した問題だとした。本書187ページで引用されている梁の「レッセフェールというハンディ」というフレーズは政府のジレンマを的確に表現している。もっとも、梁は当初から中国政府に近い人物と見られていたために、彼の意見に対しては懐疑的な見方が支配的であった。すなわち、「自由放任主義」を放棄することは中国本土の政策との一体化が進むことを示唆するのではないか、「一国二制度」が今後守られていくのか、といった不安の声が高まったのである。長く続いた失政を修正するチャンスだったはずがその機も逸するほどに、梁と香港市民の間の信頼関係が崩れていたことを物語る。
【編集注】
本稿は、『香港 失跡の軌跡』に収録された監訳者解題の抄録であり、引き続き以下の節が続いている。
4.中国本土との関係
5.生き残りの文化
また、ウェブへの掲載に当たり、改行を増やし、また、著者や狭小住宅の写真を収録するなど、ウェブ上で読みやすくする再編集を行っている。
 |
書名 | 香港 失政の軌跡─市場原理妄信が招いた社会の歪み |
|---|---|---|
| 著 | レオ F・グッドスタット 著 曽根 康雄 監訳・訳 |
|
| 出版年月日 | 2021/10/06 | |
| ISBN | 9784561913177 | |
| 判型・ページ数 | A5判・240ページ | |
| 定価 | 定価3300円(本体3000円+税) |