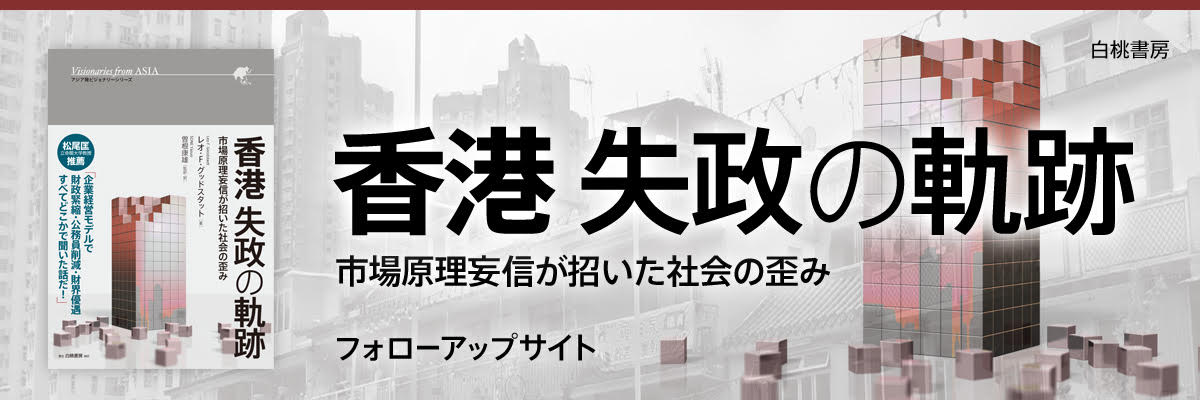2019年6月に大規模なデモが発生してから、香港は一変した。デモは約1年にわたり繰り広げられ、コロナ禍の中でもなお続いたが、2020年6月に北京の中央政府が国家安全維持法を施行したことで強引に沈静化させた。それに伴い、著名な活動家の逮捕や民主派の大手紙『蘋果日報』(りんご日報、またはアップル・デイリーと呼ばれる)の廃刊など、懸念すべき状況が続いている。
 国安法施行の要因は、もちろん香港統制の強化を望む北京の意向も濃厚に関係しているが、デモの中で参加者の一部が暴徒化し、香港社会に大きな混乱を生じさせたことも、少なからず関係したと思われる。2019年香港デモでは、従来型の理知的な抗議運動も続けられてはいたものの、暴力的抗議も積極的に行う「勇武派」と呼ばれる若者グループが台頭し、デモの顔となっていた。
国安法施行の要因は、もちろん香港統制の強化を望む北京の意向も濃厚に関係しているが、デモの中で参加者の一部が暴徒化し、香港社会に大きな混乱を生じさせたことも、少なからず関係したと思われる。2019年香港デモでは、従来型の理知的な抗議運動も続けられてはいたものの、暴力的抗議も積極的に行う「勇武派」と呼ばれる若者グループが台頭し、デモの顔となっていた。
この勇武派の若者の多くは、現代の香港社会において必ずしもエリート層とは呼べない人たちだったとみられる。そして、彼らの不満を生み出した香港社会の矛盾は、1997年の香港返還以来蓄積されてきたものだったという、香港の民生の問題点を指摘したのが、10月上旬、小社より刊行予定の『香港 失政の軌跡』(レオ・F・グッドスタット著)である。
香港の大規模デモについて、独自の視点から深層を掘り下げたルポルタージュを精力的に発表してきた安田峰俊氏に、監訳・訳を行った日本大学経済学部教授の曽根康雄氏のインタビューをお願いした。
■返還後の香港の民生問題の深刻さを描き出す
──まず、『香港 失政の軌跡』を要約すると、どういった内容になりますか?
曽根:香港では、財界と政府が利益共同体になっており、国際金融・ビジネスセンターとして繁栄することを至上命題としてきました。この経済構造は英国植民地時代から中国に返還された現在まで、一貫して変わりません。
一方、変わったのは社会構造です。香港特別行政区の初代行政長官である董建華(とう・けんか)は返還当初、公営住宅の大幅増を打ち出しました。これに庶民はワッと喜んだ。すなわち、返還後の体制の下では従来の財閥主導ではない、民生重視の政治が行なわれるのではないかという期待が生まれたわけです。しかし、この政策はアジア金融危機がもたらした経済混乱に伴い引っ込められ、結局は財界主導のまま、現在まで来てしまった。
香港返還後に生まれ育った若い世代にしてみれば、香港政府は自分たちが生まれてから一貫して財界の方しか見ていないように思える。これはすなわち、中国の方しか見ていないように見えるということでもあります。庶民の方はまったく向いていない、と。
この本は、2019年に始まる香港デモの発生以前に書かれたものですが、結果的にはデモにあれだけの若者が身を投じた理由、香港政府が庶民層の支持を失っていた理由が、その記述の中から見えてくると思います。
──あえて本書を選んで日本に紹介しようと思われた理由は?
曽根:香港の住宅や不動産関係の英語の書籍は何冊か優れたものがあり、監訳者解題の中でも紹介しています。ただ、本書の魅力はより広い視野で香港の民生問題を扱っていることにあります。
著者のレオ・F・グッドスタット氏は1960年代から香港でジャーナリスト・研究者として活躍し、植民地政府のアドバイザー的な立場にもいた人物であって、その彼が返還後の20年間を総括しています。一般の研究者やコンサルタントが執筆した書籍以上に当事者的な立場で、しかも長い目で見た記述がなされているわけです。返還後の香港の民生についての政策がきちんと整理された、今後の研究を行う上での土台となる本だと思いますね。
■返還が民生問題を悪化させた理由

インタビュアー安田峰俊氏
──2019年の香港デモの発生以来、香港の社会はデモに親和的な姿勢(黄色:民主派)か、体制に宥和的な姿勢(藍色:親中派・建制派)かで大きく分断されています。本書の場合、香港ではどういった層から受け入れられる内容だったのでしょうか?
曽根:民生問題は民主派か親中派かを問わず関心を持たれる話題ですから、いずれの層からも受容され得る内容なのだと思います。事実、刊行から数年を経ても香港のオンライン書店では本書の販売が続いていますし、中国語(繁体字)版も刊行されている。市民の関心の高さを示しているのではないでしょうか。
ちなみに、いわゆる「親中派」は既得権益層のようにも思われがちですが、何でも香港政府の政策に賛成するかといえば、それほど単純な話ではないわけです。たとえば、董建華が当初掲げていた住宅供給を増やす政策を撤回した背景には、すでに住宅オーナーとなっていた中間層からの不満が強く関係していました。公営住宅が増えると、やっとのことで購入した住宅の資産価値が下がるという懸念を持っていました。
──既得権益とまではいかずとも、持ち家がある中間層と持たない層の間では、利害衝突があるわけですね。
曽根:そうなんです。一方、一般には「親中的」とみられがちな新移民(中国大陸からの近年の移民)の立場もさまざまです。エリート層ではない一般人、特に貧困層寄りの一般人の住宅難は昔から深刻ですから、香港の旧来からの庶民層と利害は一致しています。教育についても同様です。一昔前であれば、貧困層の出身者でも教育を受けることで社会的階層を上がることができたのですが、現在それは非常に難しくなってきています。
──こうした住宅・教育問題に象徴される民生の問題は、英国植民地時代から萌芽はあったと思います。植民地時代に、現在と比較すると問題が顕在化していなかった理由は何だと思われますか?
曽根:英国統治下では、社会不安に陥る前に問題を察知して対応することは、それなりにうまくやっていたところもありました。また、植民地時代のトップは宗主国から送られてきた総督でしたから、財界も言うことを聞いていたわけです。
一方で返還後、行政長官と財界の関係が以前のようにうまくいかなくなりました。初代の董建華は本人が財界人である上、ビジネスマンとしては必ずしも成功した人物ではありませんでしたから、財界の声を無視できなかったし、また財界から軽く見られるところがありました。次に行政長官になった官僚出身の曽蔭権(そ・いんけん)も、財界や中国にいい顔をし過ぎました。結局、収賄の疑いで逮捕されることになるのですが、そのあたりの政治感覚はやはり希薄だったわけです。そして三代目の梁振英(りょう・しんえい)は、すごく評判が悪かった。

左上から時計回りに董建華(初代)→曾蔭権(二代)
→梁振英(三代)→林鄭月娥(四代)
本書序章扉より。写真は香港プレス提供
──2014年の雨傘運動でも、デモ隊の間で梁振英の不人気ぶりはすごかったですね。
曽根:ええ。そもそも市民の信認がなかった。どんなにいいことを言っても、その通りに受け取ってもらえません。梁振英は不動産の専門家ですから、住宅問題の根本的な原因は分かっていたはずですが、財界の利益を意識せざるをえなかった。
──一方、行政長官四代目の林鄭月娥(りんてい・げつが、英語名キャリー・ラムとも呼ばれる)は、香港デモと国安法施行を経た現在では市民から蛇蝎(だかつ)のように嫌われていますが、就任当初はある程度まで期待されていたそうですね。
曽根:彼女は英国植民地時代以来の官僚出身なので、梁振英と違ってバランス感覚のある人物だと思われていた面はあります。就任後の最初の1年くらいは財界からも「よくやっている」という声がそれなりにあったようです。ただ、これは庶民感覚のなさと表裏一体でもありました。2019年に逃亡犯条例改正案を出したことも、やはり彼女の世論に対する鈍感さを示したものだったでしょうね。地下鉄に乗るときのICカードの使い方すら知らなかったほどですから。
■2014年の雨傘運動と2019年のデモとの違い
──2010年代に入り、香港では2014年の雨傘運動、2019年の大規模デモという、若者を中心にした大きな異議申し立て運動が2回起きました。5年を経て起きた二つの運動について、何か違いがあると思われますか?

監訳者曽根康雄氏。バーチャル背景は湾仔(ワンチャイ)のトラム通りに面したビル
曽根:質的な違いがあると思います。雨傘運動は、行政長官の選出方法をめぐる抗議運動で、候補者が自由に立候補できないという制限に対する強烈な反発でした。ただ、あれはもともと香港に存在していなかったものを求める「民主化」というベクトルでの反発です。返還前に成人した世代の香港人の中には「もともとなかったものをねだってどうする?」と割り切って考える人もいたようですが、若者たちは求めたかった。雨傘運動への支持が必ずしも広がりきらなかった理由も、この点にあったのでしょう。
一方、2019年6月の大規模デモの引き金を引いた逃亡犯条例改正案では、中国に渡航したことがある人ならば、引き渡しの対象になり得るのではないかという不安が広がった。つまり、これまで香港人が享受してきた自由に対する制限への反発だった。そのため、雨傘運動と比べても圧倒的に多くの市民が街頭に出ましたし、途中で失速せず、世代を超えた広がりも見せた。雨傘運動との違いは、さらなる民主を目指すのか、あるいは今まで享受してきた自由を守るのかの違いだったのではないでしょうか。
──世論調査でもおおむね6割以上の市民がデモを支持し続けたのもそういうことでしょう。ただ、2019年のデモは開始から数ヶ月経つと、特に最前線では暴力の行使や都市施設の破壊といった暴走行為が目立つようになりました。
曽根:そういった前線にいた若者たちの多くは、いわゆるエリート層ではなかったと見られます。ですから、デモが暴徒化した背景として、従来の民生問題への不満というマグマが吹き出した側面があったはずです。さらに、こうした若者層の「暴走」に対して、大人たちがそれを止めなかったのは、彼らの気持ちもよく分かるという感情も関係していたと思います。自分たちも今の政府には不満があると。民主化という遠い理想を論じる以前に、住宅や教育の問題に代表される不満が多々あるにもかかわらず、政府はそれに真剣に向き合っていない。このことが、「暴走」を黙認する世論を作ってしまったのかもしれません。
──香港における大規模な反体制運動は、文化大革命期の六七暴動(1967年)を最後としてほとんど起きてこなかった。それが2010年代になり、雨傘運動と大規模デモという形で立て続けに吹き出したのはなぜなのでしょうか?
曽根:香港で生まれ育ち、香港にアイデンティティを覚える若者が増えていることが大きく関係していると思います。たとえば私くらいの世代(1950~60年代生まれ)の香港人なら、中国大陸で生まれた人も多くいます。中国大陸の文化大革命や貧困から逃れてきたとはいえ、自分が中国人だという意識は残っており、オリンピックでは英国よりも中国を応援する。これが一昔前までの香港人意識だったのですが、若者の場合は大きく違うのです。
若者の場合、中国に返還された後の「一国二制度」の下にあるという意識の中でずっと生きてきて、返還前のことを知らない。年配層からすれば、現在の香港は植民地時代に比べればインフラなど、物理的に豊かになっているし、1990年代からは多少なりとも直接選挙をできるようになったわけですから、現在はそこまで悪くはないという考え方もあり得るわけですが、若者の場合はそうはいきません。かつて植民地世代の台湾人の心情を指して「台湾人の悲哀」という言葉が流行りましたが、現在の香港には「香港人の悲哀」を意識する世代が生まれてきてしまいました。
──さらに言えば、現在の香港の悲劇は、香港自身の将来を香港で決められず、北京の習近平政権の動向といった外的な要因によって社会が左右される点にもあるのではないでしょうか。
曽根:同感です。とはいえ、どれだけ習近平政権が盤石だったとしても、それが十年後か二十年後かはわかりませんが、やがては別の指導者の時代が来ます。その時まで、「一国二制度」を定めた香港基本法が維持されれば、また違った将来を描くこともできるのではないでしょうか。本来、香港基本法には、政治制度であれ経済政策であれ、運用次第では、より自由度の高いことができる余地があります。2019年以来のデモでは、若者たちが香港基本法の枠組みすら飛び越えているところがありました。その気持ちは理解できるものの、現実的な落としどころから離れてしまっていくことを懸念していました。
──香港デモを通じて、香港社会の分断はさらに拡大しました。民主派のみならず、いわゆる親中派の人たちも含めて、香港政府への信頼性は大きく低下したと思います。信頼を失った香港政府が今後、民主化はさておき住宅・教育問題などの分野において、どのように課題を解決していくのでしょうか?
曽根:本書の解題の脚注部分で少し書いたのですが、今年(2021年)3月の施政演説では、狭小アパートに関する規制を今年中に導入する方針が示されました(その後、7月には極狭アパート賃貸管理規制草案が公表された)。また、新型コロナ対策の支出増もあったので、財源確保のため証券取引の印紙税を3割ほど増やすと。いずれも、従来の財界寄りの姿勢から、多少の方向転換を目指していることが見て取れます。
もともと、大規模デモ発生前の2019年の施政演説では、林鄭月娥は民生問題の解決についてかなり多く言及していたのですが、2020年はデモの煽りを受けて「一国二制度の堅持」といった、北京の中央政府に忖度するような政治色の強い内容になっていました。今年の施政演説は、比較的民生問題に配慮する方向へ回帰してきた印象です。
香港に対する外国の投資家の信任を維持するためには、やはり民生問題は重要なので、財界はある程度は我慢しなくてはならないというメッセージを、行政長官がこれからどのくらい発信していくかが注目されます。もっとも、これは日本企業など外国企業を含むビジネス界にとっては、負担が大きくなるということになるかもしれません。
■香港の「レジリエンス」への期待
──ところで、ビジネスの視点から昨今の香港の騒動を見ると、まったく違った景色が見えますね。
曽根:2020年の香港証券取引所のIPO(新規株式公開)による資金調達額は前年に比べ2割以上増加し,世界第2位になりました。株価も、米国には及ばないものの,コロナ禍のダメージから回復してきています。中国企業が香港市場に上場し資金調達を行っているなど、金融界は正常に働いています。中国のプレゼンスが大きくなったことは、もちろん心情的には「嫌」だと考えるビジネスパーソンもいるはずですが、それよりも儲かればいい。これはこれで「香港らしい」姿です。
──そうした姿勢は、一般には「親中派」とみなされがちでもありますが、動機は経済的な利益です。
曽根:今は政府も財界も、中国の言いなりのような感じですが、表向きはそうしたフリをしながらどうやって中国相手に上手い商売ができるか、1ドルでも多く掠め取って商売を続け拡大していこうか、と考えるのが香港人だとも思います。そういう気持ちがある限りは、香港はやっぱり香港じゃないのかなとも思えるのですよね。
この本の中で、著者は「レジリエンス」という言葉をよく使っています。困難に直面しても、したたかに、さまざまな状況の変化に対応して、それでも生き延びていく習性。香港には、このレジリエンス(生き残りの文化)が、まだ残っていると私は信じていきたいと思っています。
(2021年5月6日、ZOOMにて収録)
 |
書名 | 香港 失政の軌跡─市場原理妄信が招いた社会の歪み |
|---|---|---|
| 著 | レオ F・グッドスタット 著 曽根 康雄 監訳・訳 |
|
| 出版年月日 | 2021/10/06 | |
| ISBN | 9784561913177 | |
| 判型・ページ数 | A5判・240ページ | |
| 定価 | 定価3300円(本体3000円+税) |