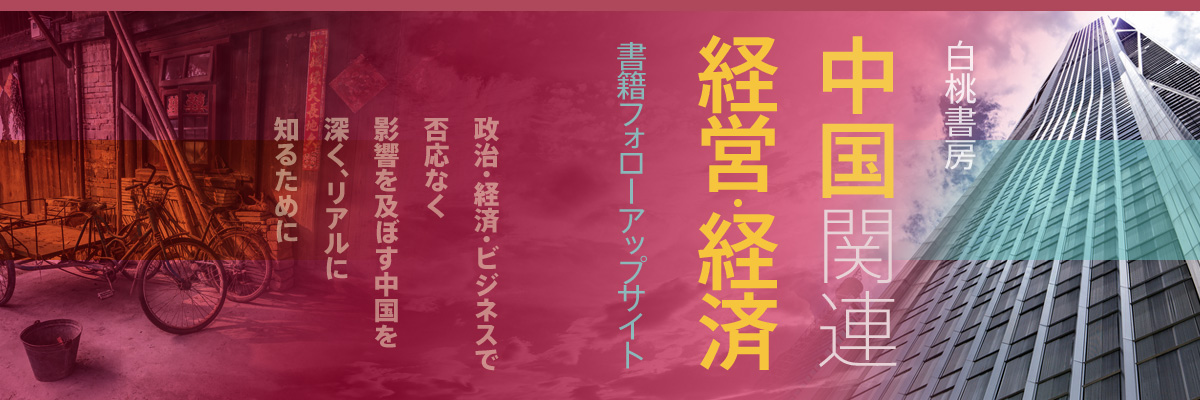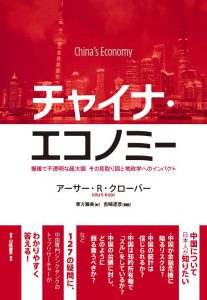 大変にご好評いただいている『チャイナ・エコノミー』について、紙版の刊行からだいぶ遅れてしまいましたが、このたび、電子書籍版も発行することになりました。
大変にご好評いただいている『チャイナ・エコノミー』について、紙版の刊行からだいぶ遅れてしまいましたが、このたび、電子書籍版も発行することになりました。
そのリリースにあたり現代中国研究家として著名な津上俊哉氏に、この本の変わらぬ魅力と、中国の現状についての読み解きをご寄稿いただきました。(白桃書房編集部)
『チャイナ・エコノミー』- 中国経済理解のためのベンチマーク
現代中国研究家・日本国際問題研究所客員研究員
本書の著者アーサー・R・クローバーは、北京(在住20年)とニューヨークを拠点にするチャイナウォッチャーで、欧米の主要紙でもしばしばコメントを見かける。謝辞に並ぶ錚々たる名前は、真贋を見分ける著者の目の確かさを感じさせる。
本書は著者の中国観察の集大成である。127の質問を立ててあるので、百科事典風に知りたい項目をつまみ読みすることもできるが、経済のみならず統治の仕組みや国際関係の未来にまで及んで、中国という国を理解するためのツボを分かりやすく説明してあるので、中国に関心ある人はぜひ通読してほしい。
中国経済については、往々にして楽観派(チャイナ・ブル(雄牛))と悲観派(チャイナ・ベア(熊))の二項対立が見られるが、著者は「慎重な楽観派」に位置づけられる。しかし、その楽観は政府の公式見解を鵜呑みにするものではなく、現地に長く暮らし、中国経済社会の巨大な変化を日々感じ取ってきた実感に裏付けられていることを感じる。また、日本の専門家は企業活動、貿易、金融など守備範囲が細分化されすぎなのに対して、著者は経済全体を鳥瞰できる広い視野を持っているのが強みでもある。
著者の中国理解の深さを感じさせられた点を幾つか挙げたい。
中国はなぜ成長できたか
その秘訣として、改革開放政策、インフラ整備、入念・巧妙な産業・技術政策などを挙げるのが中国経済書の定番であるが、本書はそれらに加えて、都市化、住宅、人口動態、戸籍などが絡み合いながら大きな役割を果たしたことを描き出している点が出色である。
例えば「都市化が経済成長と3つの形で関係している」という指摘だ(92頁、第4章。編集注:頁数は紙版、以下同様)。
最初は労働の移動である(著者は都市が労働力を惹きつける「磁石フェーズ」と呼ぶ)。改革開放によって進出した外資企業の工場など沿海部の近代的な産業に労働者が移ったことにより、元農民である彼らの生産性は大幅に向上し、それが経済成長の最大の要因となった(これは故青木昌彦教授も力説し、こんにち通説となった中国経済の成長に対する成長会計的なアプローチだ)。
2つめは住宅・都市建設ブームだ。都市部で国有企業が管理していた住宅が1998年から私有化された結果、市場価格よりもずっと低い値段で住宅を購入できた都市部の世帯には、棚からぼたもちのような巨大な利益がもたらされた(著者は「富の移転としては史上最大級のもの」と評す)。同時に都市部で多大なインフラ投資が実行され、投資の側面から経済成長を促進する住宅と都市の建設ブームが起きた。ただし、著者は農村部ではこれに相応する農地に関する財産権の私有化が行われなかったことが都市部と農村部の貧富の格差の主要因になったと喝破する。
3つ目は都市における知識サービス産業の発展、「スマートシティーのフェーズ」だ。住宅やインフラが整った後の都市には、「スキルを持った労働者の層が厚くなって知識のネットワークが生まれ、そこから特定の産業への専門家や、その産業での生産性の拡大が起きる」。
しかし、今や中国の大都市は過密問題を恐れて「人口の集中を抑制する政策をとっている」が、「都市の成長を意図的に制限すると中国はイノベーションを生み出せる社会に向けての成長が遅くなるし、戸籍制度によって生じている不平等の解消も難しくなる」とする(101頁、第4章)。
統治の仕組み
著者は中国の統治の仕組みを3つの特徴で表現する。すなわち、中国の政治システムは「一党支配」の下での「官僚制ー権威主義である」と同時に、「公式には中央集権だが、実際には非常に分権化されている」と(1~5頁、第1章)。
「一党支配」は誰でも知るが、残る2点は香港大学の許成鋼教授が「地方分権型権威主義(regionally decentralized authoritarian (RDA) regime)」と呼んだものだ。この集権と分権の絶妙な交叉は、現場感覚抜きには理解しがたい。
中国社会には事業の管理運営を任せて簡潔明快なベンチマークでパフォーマンスを監督する「請負(承包)」という永年の慣行がある。「地方分権型権威主義」は、地方行政を党書記や首長など党政幹部に任せる際に、税収やGDP成長率をベンチマークにして幹部同士を競わせる競争メカニズムを本質とするものだ。この仕組みは税収やGDP成長率さえ上げれば良かった2000年代前半に威力を発揮し、中国地方経済の成長を牽引した。
しかし、2016年ノーベル経済学賞を受賞したホルムストロームらが明らかにしたように、地方幹部(エージェント)が相互に背反する複数のベンチマーク(マルチ・タスク)を課されると、パフォーマンスが計りやすい仕事にばかり傾注するといったバイアスが発生してしまう。税収に加えて、環境も保全し、労働権も保護し、社会の安定を確保し・・・と、多数の任務を同時に課す今の中国地方分権主義は、まさにこの問題に直面しており、「情報の非対称」問題が避けられない単線型の「一党支配」では解けそうもない。
一方で、著者は分権化された一党支配がもたらす弊害を154頁(第6章)で論述するほか、権威主義的な統治システムの下ではイノベーションと想像力が犠牲になるため、中国経済・社会が成長と活力を維持したいならば、「経済成長と政治的な統制の間で二者択一をしなければならない」とも説く(31、319頁。それぞれ第1章、第12章)。
財政システムについて
今世紀に入ってからの中国の飛躍的な発展に大きく貢献した1994年の税制大改革(分税制改革)について、本書が紙幅を割いて取り上げていることに賛意を表したい。1980年代の改革開放によって、計画経済時代の国庫歳入源(国有企業の利益上納や農産物価格の鞘抜き)が駄目になった結果、中央財政は素寒貧になってしまった。
地方の既得権を保障しつつ、新規の歳入を中央財政側に思い切って傾斜させる歳入再分配を実現したこの改革は今世紀に入ってから絶大な効果を挙げ、中央財政の所得移転能力を飛躍的に高めたからだ。この改革が無ければ、中国が国内制度の統一・標準化を進めて国のかたちを整えることはできなかった。
本書は多大の成功を収めた分税制改革が、一方では深刻な弊害も生んだことを取り上げている。地方財政が窮乏して公共サービスが低下したり、赤字を埋めるための不透明で迂回的な資金調達をはびこらせてしまったことだ(164頁、第6章)。このため、習近平政権は2014年から中央・地方の財政改革に再び取り組んでいる。本書は168頁(第6章)以降でこの改革も取り上げているが、この改革は十分進んでいない。
国有企業問題について
国有企業や企業制度に対する著者の見方は明晰だ。「国有企業が経済に占める割合は減少してきているが、民間企業セクターの拡大ペースは2008年以降目立って下がって」おり(147頁、第5章)、さらに「国有企業の効率は劇的に下がっている」(150頁、第5章)と言う。
そのため、中国経済が成長を維持するためには、「民間企業が事業を行える分野を増やし、かつ国有企業を合理化することによって、効率の改善を実現する必要がある」と言う(150頁)。異論の無い見方だと言って良いが、問題は実行できるかどうかだ。
金融について
著者は胡錦濤政権の時代の中国が、銀行不良債権処理とインフラ整備促進という二つの目的のために、預金者に低金利を強い、実質預金金利をマイナスにする「金融抑圧」政策を採ったという(181頁、第7章)。賛同できる見方だ。
中国が金融危機に陥るかについて、著者は住宅ローンはレバレッジが低い(自己資金比率が高い)ので、仮に住宅価格が下落しても、家計が債務超過にならずにローンの支払いを続けられるため、サブプライム型の危機は起きないが、経済全体を通じて投資効率の低下、資産の質の劣化によって負債/GDP比率が急増していることは「深刻な懸念」だとする(183頁、第7章)。
中国には「最後はお上が債務不履行を解決する」という政府による「暗黙の保証」慣行があるので、今後も不良資産を抱える債務者が次々と急激な流動性危機に陥ることは考えにくい。地方政府や国有企業なら、たとえ債務超過で支払能力を喪失しても、上級政府の暗黙の保証が働くことが多いであろう。
しかし、負債の増大が続けば、「暗黙の保証」体制もやがて限界が来る。このため、著者は今後数年間で「融資の増加率を今の半分程度にして、GDPの成長率と歩調を合わせる必要がある」が、「成長を落とさずに融資の伸びを抑えるのは非常に難しい」とする(189頁、第7章)。
過去5年間の中国経済は、まさにこのパラドックスを地で行った。そして米中貿易戦争が起きて以降、成長を維持するために負債/GDP比率を抑えることはいよいよ難しくなっているように見える。
中国の将来について
著者は「今後20年間のどこかの時点で、中国が米国を追い越して世界最大の経済となる可能性が、決して確実ではないが存在する」とする(323頁、第13章)一方、「中国の今後の人口構成や経済の展望が不透明で、米国を追い抜ける可能性は絶対のものではない」し、「米国経済には未開拓の大きな可能性がある」、そして「米国主導の世界秩序は頑丈で豊か」なので、「中国が米国の技術的・文化的・政治的リーダーの座を奪う可能性はない」と言う(361頁、第13章)。
米国政治エリートの大多数が、今も自信を持ってこの見方を肯定できるなら、米中対立は今ほど深刻になっていないだろう。2016年春に刊行された原書は、大半が2015年に書かれたと推測するが、その後の4年間に起きた変化はトランプ大統領の登場といい、米中の深刻な対立といい、実に大きかった。著者は上記の見立てを今も変えていないだろうか、特に「米国主導の世界秩序は頑丈で豊か」という点について。
その意味で、著者には本書の続編を期待したいところだが、未来を正確に外挿するためには、中国の今を正確に認識する必要がある。その点で、中国の強みと弱みをフェアに描き出す本書は刊行後4年が経つ今も陳腐化していないと思われる。
 |
津上俊哉(現代中国研究家・日本国際問題研究所客員研究員) 1957年生まれ、1980年東京大学卒業後、通商産業省に入省、在中国日本大使館参事官、北東アジア課長、経済産業研究所上席研究員を歴任。2018年4月から現職。 著書に「中国台頭」(2003年サントリー学芸賞受賞)、「中国台頭の終焉」(日本経済新聞社刊)、「「米中経済戦争」の内実を読み解く」(2017年PHP研究所)等がある。 |
【電子書籍版へのリンク】
| 著・訳者・解説 | アーサー・R・クローバー 著/東方 雅美 訳 /吉崎 達彦 解説 |
|---|---|
| 電子版発行日 | 2019/08/26 |
| ISBN | 9784561991397 |
| 価格 | 本体2315円+税 |