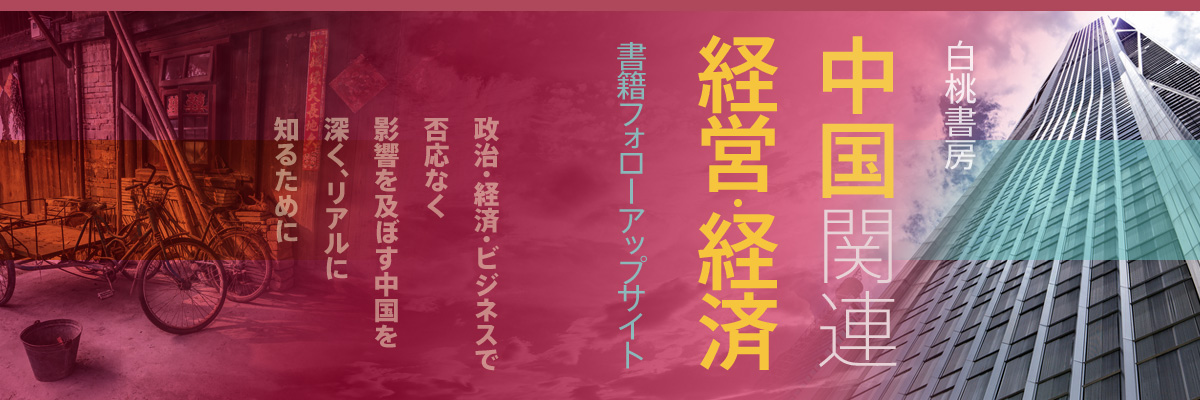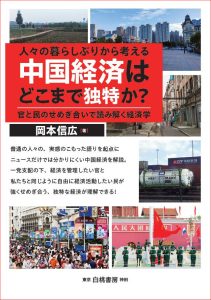 中国の街には「城管(じょうかん)」と呼ばれる役人がいます。彼らは都市管理を担う公務員であり、日本語では都市管理員と訳されています。彼らの仕事は、都市の安全、衛生、環境を守るためという名の下で、人々の行動を取り締まることです。一般に、彼らは市民から嫌われています。
中国の街には「城管(じょうかん)」と呼ばれる役人がいます。彼らは都市管理を担う公務員であり、日本語では都市管理員と訳されています。彼らの仕事は、都市の安全、衛生、環境を守るためという名の下で、人々の行動を取り締まることです。一般に、彼らは市民から嫌われています。
都市管理員によく取り締まられているのが露天商です。他の途上国と同じように、中国では人通りの多い道路沿いや広場で露天商をよく見かけます。農村から出てきた農民たちが豊かになりたいという気持ちで、町の道端に簡易な屋台を設置し、朝食用に揚げパンやアツアツの肉まんを売ったり、羊肉を使った焼き鳥のような食べ物である羊肉串を販売したり、自分の畑で採れた果物を並べたり、市場で仕入れた食器や雑貨類を簡易な机に並べて販売したりしています。人々は通勤途中で肉まんを購入し、リタイアした老人が雑貨類を眺めながらゆっくり歩いています。このような露天商は人々の自由な経済活動として行われており、街の賑わいの一つとなっています。
しかし露天商の営業は、都市の景観、食品衛生、商品の質などで問題があることがあります。そこで都市管理員がやってきて、許可証の提示を求めたり、景観を理由に強制的に排除したりとさまざまな取り締まりを実施します。「安心安全な都市建設」というような政府のスローガンの下、露天商の自由な経済活動を取り締まるのです。
露天商の人々は取り締まりを受けても、露天商という経済活動を素直にあきらめることはありません。屋台を出店している農民にとって営業を取り締まられるのは、収入を失うことになります。そこで、取り締まりを避ける工夫を行います。例えば、都市管理員と個人的につながりを持って、取り締まりの日時を早めに教えてもらったり、家族のうち誰かを見張りに立て、都市管理員が来るかどうかを監視させたりします。あるいは、取り締まりが少ないけれども人通りが多い別の場所を探したりとさまざまな工夫をしています。でもこれらがうまくいかなければ、逃げ通すことができずに捕まることもあります。
一方で、政府で働く都市管理員のような公務員も普通の人々です。生活のために政府の役割としての仕事をしているのが実情です。彼らも制服を脱げば、家で子どもの勉強をみたり、休日にはスーパーに行ったりレストランに行って家族と過ごしています。その中には共産党員もいて、意識高い党員は中国のために熱い思いを持って、屋台の取り締まりという仕事をしています。もちろん中には、権力に魅せられた打算的な党員もいて、取り締まりの権力を利用して、農民から袖の下を受け取ることもあるでしょう。
中国では露天商のような、人々の自由な経済活動が積み重なることで、経済が発展してきました。時には都市管理員のような政府の取り締まり、あるいはもっと大掛かりな、政府の通達や法律の改正が人々の行動に影響を及ぼします。時には一部の地域で屋台の出店禁止が決まったり、町の外れの特定の場所に追いやられたりします。それでも人々は、新しい規制や取り締まり中でも、さまざまな工夫をしながら経済活動を続けています。
このような現象は中国で「上に政策あれば下に対策あり」と言われます。この言葉は、中国4000年の歴史の中で、各王朝の取り締まりとそれに対応してきた庶民の工夫を示すものと言っていいでしょう。
この政府の取り締まりと人々の対応は、中国経済を形成する重要なパーツで、現在の中国経済を理解する上で欠くことができない視点です。これが中国経済を独特なものにしている大きな要因となっています。本書では、ここで描いた、都市管理員に代表される政府の関与と、出稼ぎ農民に見られるような、自由な経済活動の間のせめぎ合いという観点から中国経済を見ることで、中国経済は私たちとどう違うのか、どこが独特なのかを分析し、解説しています。
普段、日本の私たちは、報道などで伝えられる、中国の政治指導者たちや外交スポークスマンのような人たちに注意が行きがちです。しかし、世界第二位となり、地球規模で大きな影響を与えている中国経済と言えども、露天商のような小さな事業から大企業、あるいは政府に至るまで、さまざまな舞台において、労働者やビジネスパーソン、農民、経営者、役人や官僚たちが経済活動を行った結果の総体に過ぎません。
そこで、本書は中国経済の入門書として、経済について語るにあたり、人々の生きざまを起点にして、中国経済をつかんでいただくことを試みました。国として4000年余の歴史を持ち、独自の仕組みを持った中国は、このようなミクロの視点からの理解も欠かせません。そして、人々の生活に視点を置いて中国経済を解説する本書は他に類を見ないものだと考えています。
屋台を出す農民の人々の意思決定、政府で働く都市管理員の人々の意思決定、これらがせめぎ合いながら中国の経済活動は形作られていきます。その結果、中国経済は「改革開放」以降の約半世紀でGDP(国内総生産)は約40倍(実質値)になりました。発展した要因は、政府で働く都市管理員が農民の屋台が自由に出せるようにした結果でもありますし、そのチャンスを農民がしっかりつかんだからです。
経済学的観点から言えば、彼らの経済活動のうち、どちらが正しい、正しくないという道徳的な判断は必要なく、いわんや中国経済全体としてもいい悪いという判断をする必要もありません。
すなわち中国において「政府と市場のせめぎ合い」の過程でどのように多くの人が豊かになってきたのか、最近の経済状況はどのような「政府と市場のせめぎ合い」から発生しているのか、といった観点から中国経済を見る方が得るものが多いと筆者は考えています。
この「政府と市場のせめぎ合い」への理解が深まれば、日本に住む私たちの生活や日本経済においても、政府の関与や生活の自由を考える糧にもなると信じています。
| 著 | 岡本信広 |
|---|---|
| 出版年月日 | 2025/04/06 |
| ISBN | 9784561961451 |
| 判型・ページ数 | A5・320ページ |
| 定価 | 本体3000円+税 |