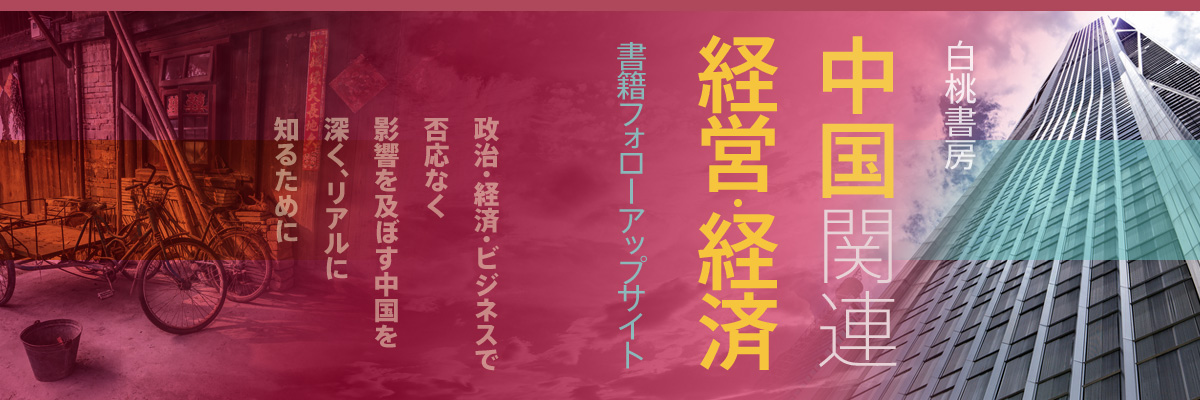1.章構成と発表時期
本稿では、『現実世界と対話する経済学』について、地域研究の視点から本書の読みどころと意義を紹介する。まず全体の流れを知るために,章構成とその発表時期を確認しよう。本書は論文集なので,各章には元になった論文がある。それらがいつ書かれたものなのか,に注目したい。というのは,周知のとおり中国の学術界および言論環境は,改革開放の動きとともに揺れ動いたからである。日本語版序文で周が述べたように,中国の改革が「前進したかと思えば後退し,または左に振れたら右に振れる,ということが繰り返される」(ii ページ)中でいかに形成されたのか,を読者は実感できよう。その意味で,本書は優れた研究書であるとともに貴重な時代の証言録でもある。
これらの点を意識して,各章の後に( )を入れて,元論文の発表年と著者の年齢を示してみた(*)。その結果は,以下のとおりである。
序文 日本語版への序文(2023年4月・72 歳),旧版序文(2002年4月・51歳),新版序文抜粋(2017年6月・66歳)
第1章 現実の世界における経済学―コースの経済学的方法論およびその中国における実践(1996年・46歳)
第2章 人的資本の財産権とその特徴(1996年9月執筆・46歳)
第3章 農村改革:経済システムの変遷を回顧する(1993-94年執筆・43-44歳)
第4章 農民,市場と制度改革―生産責任制後に農村が直面した深層における改革(1986年10-12月・36歳)
第5章 農地の財産権と土地収用制度―都市化で求められる,重要で大規模な改革(2003年・53歳)
第6章 市場における企業―人的資本と非人的資本との特別な契約(1996 年・46歳)
第7章 「コントロール権という報酬」と「企業家がコントロールする企業」―公有制企業における起業家の人的資本とその財産権に関する研究(1997 年・47歳)
第8章 公有制企業の性質(2000 年・50歳)
第9章 企業理論と中国の改革(2008 年・58歳)
第10章 競争,独占と規制―「反独占」政策の背景報告(1999 年7 月脱稿・48歳)
第11章 病気になったら,誰が面倒を見てくれるのか?―新たな医療改革計画をめぐる議論(2007-08年・57-58歳)
第12章 貨幣制度と経済成長(2007-08年・57-58歳)
第13章 体制コストと中国経済(2017年・67歳)
以上のように,本書は主として1990年代後半から2000年代後半の間に発表された論文を収録している。年齢でいえば,著者が40代半ばから50代後半にかけての働き盛りの時期であり,政治状況としては江沢民時代から胡錦濤政権の前半に当たる。経済面では国有企業の所有制改革が本格化し,WTOへの加入が実現するなか,中国は新たな高度経済成長の段階に入っていた。社会では都市化が進み,生活水準が急上昇する一方で,貧富の格差が広がっていた。また携帯電話の利用が爆発的に広がり,思想・言論界では大胆な議論が活発に展開され,一部の知識人は三権分立や人権,民主化を求める零八憲章を発表した。本書に収められた周其仁の論説は,こうした時代の活力を反映すると同時に,経済改革の進むべき方向性を指し示している。
2.本書の内容
まず序文には,著者の問題関心が簡潔に記されている。中国経済が奇跡のような成長を遂げることができたのは,なによりも「体制コスト」を引き下げたことによる,と著者は断言する。「体制コスト」とは,経済システムの運用コストを指している。中国が改革開放期に世界の工場として台頭したのは,安くて豊富な労働力を利用できたから,と思われるかもしれない。しかし計画経済期にも同じく大量の安価な労働力が存在していたのに,高度経済成長にはつながらなかった。したがって問題は労働コストではなく,計画経済というシステムを動かすコストが高かった,ということにある。改革開放期の経済成長は,この体制コストを削減することで成功した,と周は考える。
それでは,なぜ計画経済の体制コストは高かったのか。体制コストがどこまで高くなると,変革を求める動きが起こるのか。変革のなかで新たに生まれた財産権に対し,国の態度(たとえば侵害するか,それとも保護するのか)を決定する要因はなんなのだろうか。そもそも,これらの問いに答えるには,どうすればいいのか。
第1章は,最後の問いに対応している。まず周は,ロナルド・コースの研究手法を紹介したのち,中国経済を理解するためにはコースのように(1)現実世界に根差した事例研究が重要であり,(2)調査においては具体的な制約条件に焦点を当てること,また(3)事例研究から得た認識を一般化して,応用の範囲と理論枠組を広げることを提言している。次に著者は,書評の形を借りて中国人研究者が執筆した複数の論文をとりあげ,上記の手法に照らした批評を行う。周が評価した事例研究は,家電製品の生産や外国為替取引,通信産業の新規参入,民間の株式取引など多岐に及ぶが,いずれも新たな経済活動の現場から生まれた工夫や適応方法を示しており,1990年代前半における市場の台頭と行政の制約の現実を知ることできる。
第2章は,本書全体に通底する「人的資本」の本質を論じている。金銭や土地などの他の資本とは異なり,人的資本(たとえば労働力や才能)は個人から切り離すことができない。人間には意思があり,他人が個人の「人的資本」を完全に支配するのは難しいからである。人を物として扱う奴隷制度においてさえも,このことが当てはまる。
周は,米国南部と西インド諸島の奴隷の身請けに関するバーゼルの論文を紹介して,次のように説明する。奴隷の所有者が奴隷の人的資本を最大限に利用しようとすると,怠けないよう一日中みはったり指示したりする必要がある。これらに費やす時間と労力は奴隷主にとっても多大な負担になる。そのような監督コストや規制コストを軽減するには,奴隷が自発的に働くようにすればよい。そこで一部の奴隷主はノルマ制を取り入れて,ノルマ超過分を奴隷自身が所有できるようにした。その結果,奴隷のなかには自分自身を身請けできるほどの財産を蓄積する者が現れた。
周はこの歴史上の例を用いて,中国では計画経済期に職業選択の自由がなく,戸籍によって移動も制限されていたが,それでも人的資本がもつ「私有財産」という本質は変わらなかった,と主張する。このことを農村改革の展開によって証明したのが,第3章から第5章である。土地革命から人民公社,生産請負制を経て郷鎮企業の急成長にいたる過程を,「財産権」と「体制コスト」というフィルターを通すことで,論理的な一貫性をもって明晰に整理しており,非常に読み応えがある。
第3章は人民公社の非効率・高コスト体質を分析し,それが限界に達して生産責任制が導入されるまでの仕組を論じている。第4章は,経営請負制度の拡大および農産物の政府統一買付からの脱却,郷鎮企業の形成と発展を描いている。この時期に,中国農村では新しい財産権を保護するメカニズムが発生していた。それは西欧近代化のような市民社会による政府への牽制とは異なり,「家族=村落コミュニティ=地方政府」の連合体と中央政府の間に繰り広げられた公式/非公式の交渉を通じて実現した,と周は考えていた。また,そうして農地の私的な使用権が確立したことから,続いて土地の収益権と譲渡権も確定されるものと,彼はこの時点では楽観的に推測していた(序文, xiv)。
しかし農地の譲渡権を明確化する動きは遅々としており,やがて都市化の波のなかで政府による農地の強制収用という形をとって深刻な問題と化した。第5章は,地方政府が農民の土地使用権を保護せず,独占的な収用によって財産権を侵害した多数の事例を分析している。これらの例では,前述の家族・村落コミュニティと地方政府の連帯は崩壊し,激しい衝突に転じている。この問題の根幹には,集団所有制のもとで農民には土地の譲渡権がない,という財産権の欠陥がある。周はこれを指摘したうえで,譲渡権の再定義と実現可能な政策提言を試みている。
第6章から11 章は,公有制企業の改革を扱っている。周は,第7章で企業における人的資本の財産権を理論面から論じたのち,第7章では実在の企業調査の結果を示している。ここでは,公有制企業において経営者の人的資本がどう評価され,報酬に結びつくのかを観察し,企業の経営決定に関わる「コントロール権」が彼らにとって重要な報酬であることを周は指摘する。読者は,人民公社の幹部報酬に関する第3章の記述を思い出すであろう。幹部らは人民公社の生産を管理・監督するのに多大な労力を投じても,大した昇進や経済的利益を期待できなかったが,「管理する権限」そのものを報酬として利用していた(p.54)。これと同様に公有制の制約下では,企業の管理職もその能力(=人的資本)を自発的に発揮する仕組として,「権限」を経営のインセンティブに転換していたのである。
しかし,このような方法には大きな欠陥がある。コントロール権が報酬として有効に機能するためには,経営者は常にその座に居続けなくてはならないからである。経営から退くことを意識すると,コントロール権はインセンティブとしての価値を失う。それを防ぐためには,たとえ能力が衰えても管理職は永遠に経営に携わらねばならない。このジレンマを解消するには,経営者の人的資本(能力)を所有権に振り替えればよい。人的資本を「資本化」して,たとえば株の形で所有できるようにすれば,経営から身を引いても収益を得ることができる。しかし公有企業の場合,この手続きは簡単にはいかない。
評者の私見では,この考察は90 年代の郷鎮企業の盛衰を見事に解き明かしている。成功した郷鎮企業には,しばしばカリスマ的な創業者がいた。名目上は農村の集体所有の形をとっていたが,実態は創業者の個人経営であった。これらは「赤い帽子をかぶった」(名ばかり公有制)企業と呼ばれ,短期間に成長して市場シェアを広げた。ところがカリスマ創業者の年齢が上がり企業の継承が問題になると,それまでの勢いを失うものが少なくなかった。その一方で,所有権を村から買い取って,赤い帽子を投げ捨てる経営者も現れた。当時を記憶する者には,周の解釈は大いに説得力がある。
第8章から第10章は,公有制企業が追求する国家レントと市場経済における利潤最大化の違いを整理し,企業コントロール権の濫用や独占禁止について考察し,対応方法を模索している。第11章は,これらの論点を体現した問題として「看病難,看病貴」(患者が診療を受けにくく,医療費も高騰したこと)を取り上げている。一部の研究者は「医療の市場化」がその原因だと主張していたが,周はこの考えに反対する。そして実際のデータを用いて,増大する医療の需要に医療資源(医者,病院)の供給がまったく追いついていないことを説明し,その背景には公立病院に対する政府の統制があること,私立病院の参入は法的には認められているものの,税制上の不利益などで競争的な環境が整備されていないことを指摘する。周によれば,供給不足はひとえに政府が病院の経営に対して「口は出すが金は出さない」ことに端を発している。したがって真の問題は「医療の市場化」ではなく,逆に「市場化の不徹底」にある。
第12章は,中国が直面したインフレの構造とこれに関連する人民元の為替レートについて,マネタリストの理論から解説している。周は2000年代の構造的なインフレと不動産・株式市場バブルにおいて,政府がマネーサプライの増大という根本的な問題を議論せず,行政命令や土地の供給量の直接管理,産業・企業への直接介入に依存したことを批判する。同時に,諸外国による人民元の切り上げ要求に対して「外圧に屈するな」と叫ぶ世論に向けて,インフレと為替レートの仕組を説明するのが経済学者の責任である,という。
最後に登場する第13章は,本書のなかで唯一2010年代に発表された論考である。ここで周は再び,中国経済の加速と減速を「体制コスト」の視点から観察する。これまでの章とは逆に,本章の焦点は減速をもたらす「体制コストの上昇」に当てられている。周の考えでは,体制コストは費用の一種であるため,一般的な費用の法則――いったん下落したのち上昇に転じること――に従う。実際に中国の体制コストは改革開放で下落したが,その後の高度成長の過程で再び増大した。その勢いは,経済成長率を上回るだけでなく,生産コストなど市場で取引される他のコストと比べても早いスピードで膨張している。ここから周は,中国には体制コストを継続的に抑制するメカニズムが確立していないこと,体制コストにはある種の腐敗も含まれること,それはイノベーションとベンチャー企業とりわけ企業家精神にダメージを与えることを指摘し,したがって中国経済の持続的な成長を実現するためには,体制コストを引き下げる不断の改革が必要である,と呼びかける。行間から著者の危機感が滲む章であった。
(*)年齢については,発表月が本書に明示された章には満年齢を,不明の場合は当年の数え歳を示した。なお周其仁は1950年8月生まれ。また発表年は掲載年とするが,執筆年がわかる場合は年の後ろに「執筆」と記入した。なお第9章と第11章の出版年は本書に明記されていないが,第9章については広東人文学会等が主催した「改革開放30周年記念シンポジウム」での講演録が元になったことは記されている。そこで広東省の地元紙『南方週末』のウェブサイトで当該シンポジウムおよび周其仁の講演録を確認し,その掲載年を( )内に示した。また第11章については,2008年発行の『病有所医当問誰』(北京大学出版社)の一部だが,その中には2007年1月から『経済観察報』に連載された記事も含むため,ここでは2007-08年とした。
 |
澤田ゆかり/さわだ ゆかり 東京外国語大学総合国際学研究院・教授。1986年東京外国語大学大学院地域研究科修了。特殊法人アジア経済研究所、香港大学アジア研究センター客員研究員、神奈川大学外国語学部助教授などを経て、現職。研究分野は、地域研究(現代中国)、社会保障論。編著に『植民地香港の構造変化』(アジア経済研究所)、共編著に『高まる生活リスク ─社会保障と医療 (中国的問題叢書10)』(岩波書店)、『ポスト改革期の中国社会保障はどうなるのか』(ミネルヴァ書房)ほか。 |
(編集注)本稿は、澤田ゆかり氏(東京外国語大学大学院教授)が『現代中国研究』(中国現代史研究会発行)第53号に寄稿された『現実世界と対話する経済学』書評のIとIIの抜粋である。掲載にあたり、抜粋した部分だけで意味が通るよう、冒頭の記述を補った。
| 著・訳・監訳 | 周 其仁 著/劉 春發 訳 /梶谷 懐 監訳 |
|---|---|
| 出版年月日 | 2023/11/6 |
| ISBN | 9784561961420 |
| 判型・ページ数 | A5・400ページ |
| 定価 | 本体5636円+税 |