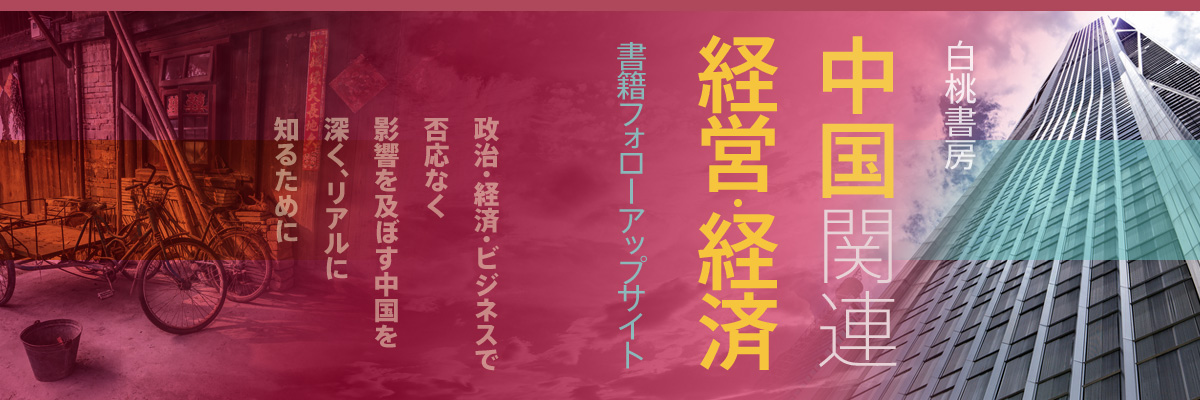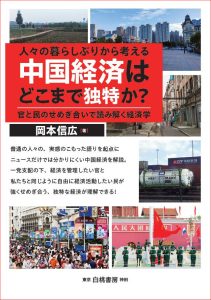 2025年6月27日、大東文化大学経済研究所にて、国際関係学部の岡本信広先生による「『中国経済はどこまで独特か』の枠組みは実際の中国経済にどこまで妥当するか?」と題した講演が行われ、担当編集Tも参加し聴講してきました。
2025年6月27日、大東文化大学経済研究所にて、国際関係学部の岡本信広先生による「『中国経済はどこまで独特か』の枠組みは実際の中国経済にどこまで妥当するか?」と題した講演が行われ、担当編集Tも参加し聴講してきました。
この講演は、岡本先生の著書『人々の暮らしぶりから考える 中国経済はどこまで独特か』を基に、この本で提示した、中国経済を理解するための重要な視点である「官と民のせめぎ合い」に特にフォーカスを当て、本の概要の紹介から始まりました。そのポイントは下記の3つです。
- 「せめぎ合い」のフレームワーク
- 民間が活躍していく過程
- 政府が関与する過程
岡本先生は、中国経済を「社会主義と市場経済の共存」というユニークな視点から分析しています。その核心にあるのが、政府の政策と人々の経済活動、すなわち「官と民のせめぎ合い」です。この「せめぎ合い」は、「民間が活躍していく過程」と「政府が関与する過程」に大きく分けられます。
改革開放以降の中国経済は、市場に親和的な政策を通じて民間部門が大きく発展してきました。社会主義計画経済から市場経済への移行における「請負制」の導入は、民間が活躍する過程の始まりと評価されています。国有企業改革による市場競争の促進と民間企業の活動容認、労働・資本の移動自由化による生産拡大と輸出主導型経済への発展、そして貿易管理からの民間企業の国際取引への自由参入、中国企業の海外進出の促進が挙げられます。EV(電気自動車)産業の成功は、政府の政策が市場の競争を促進し、規模の経済をもたらした好例です。
一方、中国政府は経済成長に伴う様々な社会課題に対し、積極的に介入してきました。都市と農村の分断や地域間格差といった経済格差の是正、食料やエネルギーの確保、環境保護のための強い政策介入(規制、補助金)、一人っ子政策に代表される人口動態への介入とその反動としての少子化対策や都市化の推進が行われています。共産党は公共の利益と個人の利益のバランスを取りながら経済資源の配分を決定しており、党大会や中央政治局委員会がその中心を担っています。
また、中国経済の今後の展望と課題についても、独自の分析に基づいた見通しを語られました。同書最終章にまとめられているように、中国経済は、地方政府の融資プラットフォーム問題(債務)、労働者数の急減を伴う人口減少、そして国際関係の悪化(デカップリング)という三つの大きな課題に直面していること、政府の政策が経済発展に効率的に機能するためには、政策の信頼性と明確なコミットメントが不可欠であることを、改めて岡本先生が指摘しました。近年の学習塾禁止の突然の指示やアリババに対する締め付けのような、恣意的な政策は経済活動を縮小させる危惧があるとのことです。
そして、結論として、岡本先生は「官と民のせめぎ合い」というキーワードが、社会主義と市場経済が共存する中国経済の可能性を理解する上で極めて有効であると強調しました。公共の利益を追求するために個人の自由を制限する政府の強い介入と、競争環境の中で活力を生み出す民間部門の力が、常にせめぎ合うことで中国経済の独特な発展を形作っていて、このダイナミズムこそが、中国経済の今後の動向を読み解く鍵となると締め括りました。
質疑応答
大東文化大学の構内で行われ、また出席者も同学の教員・学生が中心だったため、忌憚ないながらも、和やかな雰囲気で、コメンテーターからのコメント、また参加者からの質問が出て、「政府と市場のせめぎ合い」というフレームワークが多角的に掘り下げられました。
- 「政府と市場」
- 「せめぎ合い」の多義性
- 混合市場体制と国有企業
- コミットメントの「コスト」
コメンテーターの内藤先生は、中国経済は変化の激しい情勢や政策動向により、その分析や解説において時宜を得た情報が求められるため、長期間にわたって参照可能な著作を生み出すことは非常に困難である。そのような中で、本書は政府と市場という明確な視点に基づいて中国経済を分析しており、実態を理解するうえで極めて有益な成果である。こうした点からも、本書は今後継続的に貢献し得る価値ある業績であろうと述べられました。
また、内藤先生は、中国政府は改革開放以降、例えば所得再分配のような本来政府がやるべき最も重要な仕事をあまり積極的に行わず、逆にあたかも民間企業のように利益追求に関心があるような、いわゆる「企業家的行動」をとってきたという点で非常に特徴的であり、この点からも、本稿の内容については、「官と民」より「政府と市場」という表現の方がよりしっくりくると指摘しました。また、国有企業は国の経済や社会、国民の生活のためというより、むしろ国策を強力に進めるための存在でもあり、手厚く管理、保護されており、そのことが「既得権益」を生み出し、経済構造を歪めていると述べました。さらに、中国は「1から10」への改良は得意だが「0から1」のイノベーションは苦手であると同時に、新たなイノベーションが生じた際に、しばしば政府の介入が民間の活力を削ぐケースが少なくないように思われ、非常にもったいないように感じられることが多い、と指摘しました。
もう一人のコメンテーターである森先生は、「せめぎ合い」という言葉が対立的な意味合いで受け取られがちだが、共生していく側面も含まれていると理解できるのではないかと指摘した上で、このワーディングがどのように決められたのかを質問しました。岡本先生は、「共犯関係」といった言葉も検討したが、「せめぎ合い」には対立だけでなく「バランスを取る」というニュアンスも含まれることから、これが一番しっくりきたと述べました。また、森先生からは、民間が官に積極的に順応していくような「せめぎ合わない成長」や、政府の関与が非常に強く民間が従うしかないケース、あるいは誰の利益にもならない「マイナスのせめぎ合い」といった視点も提示されました。岡本先生はこれを「市場親和的か、反親和的か」という分類で捉えられると応じました。
ある参加者から、「混合市場体制はほとんどの国に当てはまるのではないか、日本と中国で何が違うのか」という質問が出ました。岡本先生は、中国の国有企業は資産で見ると、概算で企業全体の約2割を占め、巨大な国有企業の存在が日本との違いであると説明しました。
なお、後日、岡本先生に教えていただきましたが、中央国有企業、国有独資の有限公司の資産が約15%近くで、それ以外に国有経済が所有する民間企業の株式を考慮するともっと大きいかもしれないとのことです。
司会者からは、政府の政策に対する「信頼(コンフィデンス)」を確保するためには、ゲーム理論におけるコミットメントのように、政府のメッセージに、何かしらの政府が負担する「コスト」がかかっていなければ信用されないのではないか、という問いが投げかけられました。これに対し岡本先生は、最近の習近平主席が民間企業の若手社長を集めて座談会を開いた例を挙げ、これまで国有企業重視だった方針から民間企業を応援する強いメッセージが出されたことを、その「コスト」の一例として示しました。この動きは、一般の中国人が、誰が何を重視しているかを通じて、党や政府の方向性を読み取る傾向がある中で、「民間企業は頑張っていいんだ」という応援メッセージとして受け止められたと説明しました。
編集者より
私が出版のお手伝いをした本が、このようにさまざまな議論を誘発したことに大変やりがいを感じました。
また、昨今のさまざまな問題を見るにつけ、市場が万能ではなく、いろいろな形で政府が関わることが求められているように思います。中国の「官と民」あるいは「政府と市場」のあり方をつぶさに見、理解することは日本や他国の経済運営のあり方を考えていく上のヒントになると、改めて思いました。(文責:編集T)
| 著 | 岡本信広 |
|---|---|
| 出版年月日 | 2025/04/06 |
| ISBN | 9784561961451 |
| 判型・ページ数 | A5・320ページ |
| 定価 | 本体3000円+税 |